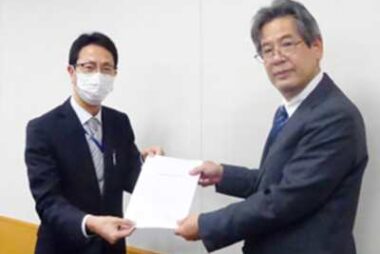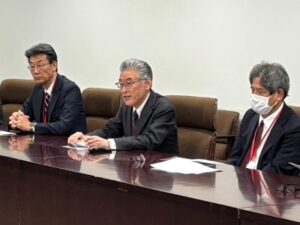私たちは、国・地方自治体・学校・病院・福祉施設など、全国各地の公務・公共職場で働く正規・非正規の労働者で組織する労働組合です。
最新の話題
- 一般職の国家公務員給与法の成立にあたって(談話)一般職の国家公務員給与法の成立にあたって(談話) 2025年12月16日 公 務 労 組 連 絡 会 事務局長 香月 直之 1.本日、第219回臨時国会において、一般職国家公務員の給与法案が参議院本会議…
- 公務ネットニュースNO.1156(12/11)ミサイル買うより暮らしと命を守る予算を = 公務部会が財務省前で宣伝行動 = 全労連公務部会は12月11日、退庁時間に合わせて「財務省前要求行動」に取り組みました。夕闇せまる霞が関で、25秋年闘争ビラを配布しながら横断…
news
2025年12月11日ミサイル買うより暮らしと命を守る予算を
= 公務部会が財務省前で宣伝行動 =
全労連公務部会は12月11日、退庁時間に合わせて「財務省前要求行動」に取り組みました。夕闇せまる霞が関で、25秋年闘争ビラを配布しながら横断幕を掲げ、公務・公共職場の人員増と予算確保をアピールしました。各組合から70人が参加しました。
ケア労働者の増員と賃上げは住民の声
はじめに公務部会の福島代表委員は、「物価高対策の給付金などの補正予算案が審議されているが、消費税の減税こそ実施すべきではないか。さらに防衛費の上積みで、当初分と合わせて約11兆円にもなる。軍備拡大競争では平和を守ることはできない。公務・公共サービス、教育拡充のために必要な予算を求める」とのべました。
各単産の代表が次々と宣伝カーに登壇し、官庁街を行き交う人たちに訴えかけました。
○教員の労働時間適正化にむけて、約52万人の教員を増やす必要がある。統廃合による学校規模の適正化ではなく、先生を増やすことこそ住民や子どもたちの声だ。(全教・板橋中央執行委員)
○退職者、休職者が補充されず、職員の努力に頼っている。時給契約社員は、最低賃金額が改定されなければ時給が上がらず、怒りしかない。均等待遇と大幅増員で、郵政会社は責任を果たせ。(郵政ユニオン・谷川中央執行委員)
○コロナ禍のもとでもケア労働者は、命をかけて現場を守ってきた。看護師の賃金はコロナ前から変わっていないばかりか、ボーナスがカットされている病院もある。政府は、軍備増強ではなく、医療や介護で働くケア労働者のために予算を使え。(日本医労連・油石書記次長)
○国立病院機構は1千億円規模の資金残高あるにもかかわらず、人件費にあてようとしない。慢性的な人員不足がサービスの低下につながっている。軍拡路線よりも社会保障制度の充実のための予算確保を求める。(全医労・岩谷中央執行委員)
○補正予算案では、介護職に対して最大で1万9千円の賃上げ策が盛り込まれた。それでも全産業平均と比べれば、大きな賃金格差がある。どのような計算をしたら1万9千円になるのか教えてもらいたい。(福祉保育労・仲野書記長)
○昨年の診療報酬引き下げで、赤字経営で検査機器の修理ができない自治体病院が多くある。社会保障は国が守るべきものであり、高市内閣はミサイルを買うより社会保障の予算を増やせ。(自治労連・山本副中央執行委員長)
行動の締めくくりに、参加者全員で財務省にむかってシュプレヒコールを繰り返し、意気高く宣伝行動を終えました。
以上 [...] Read more...
2025年11月11日25年人事院勧告の「完全実施」を回答
= 人勧の取り扱いめぐり内閣人事局と最終交渉 =
公務労組連絡会は11月10日、25年人事院勧告の取り扱いおよび「公務員賃金等に関する要求書」をめぐって政府・内閣人事局と最終交渉に臨みました。内閣人事局側は、翌11日の閣議において勧告通りの実施を決定すると回答しました。
交渉には、公務労組連絡会から檀原議長を先頭に、福島副議長、香月事務局長以下幹事会5名が参加、内閣人事局は次田総括参事官補佐ほかが対応しました。
勧告の「完全実施」の閣議決定をうけて、公務労組連絡会は11日に幹事会声明(別記)を発表しました。
勧告実施だけでは物価上昇に対応できない
最終交渉にあたって檀原議長は、「正規・非正規すべての公務労働者の労苦に報いるために、早期の賃金改善、地域間格差解消を求めてきた。その他の要求をふくめて誠実な回答を求める」とのべ、次田総括参事官補佐からは以下の回答が示されました。
<政府・内閣人事局の最終回答>
● 本年度の国家公務員の給与の取扱いについては、人事院勧告制度尊重の基本姿勢の下、検討を続けた結果、明日、勧告どおり令和7年度の給与改定を行うとの取扱方針が決定される方向である。
その上で、後日、給与改定に係る法律案についても決定されることとなる。
● 国家公務員の働き方改革については、多様な働き方を実現し、職員がやりがいを持って、高い成果を効率的に上げられるようにすることが優秀な人材の確保のためにも重要であると考えている。こうした取組については、現場の実情を含め、皆様からもご提案をいただきながら、しっかりと前に進めるのでご協力をお願いしたい。
以上の最終回答をうけて檀原議長は、「要求をしっかりと理解したものとは思えず、きわめて不満だ。物価上昇を上回る賃上げの必要性を高市首相がのべているように、政府として人事院勧告の水準にとどまるのではなく、公務員賃金の積極的な引き上げを決断すべきだ」と表明しました。
また、香月事務局長はじめ交渉参加者からは、勧告直後の8月8日に提出した要求書をふまえつつ、賃金改善とともに、非正規職員や再任用職員の処遇改善、長時間労働の解消、公務職場の大幅増員、労働基本権の回復などを求めました。
職場の実態をふまえた切実な要求にもかかわらず、政府・内閣人事局側からは「皆様方の御意見はしっかりと承った。引き続き、皆様方との意思疎通に努めてまいりたい」と、型どおりの発言にとどまりました。
最後に檀原議長は、「人事院の報告では、職務・職責をより重視した新たな制度への転換が示されたが、理不尽な格差を持ち込むことに反対する。正規・非正規の格差をはじめあらゆる格差の解消は、引き続く重点課題だ。臨時国会での議論を注視していく」とのべ、内閣人事局交渉を閉じました。
以 上 [...] Read more...
2025年10月29日公共ささえるケア労働者の処遇改善を
= 夕方の有楽町駅頭で宣伝行動 =
全労連公務部会・公務労組連絡会は10月29日、JR有楽町駅前で「いっしょに実現!物価高をこえる 大幅賃上げ!」を掲げて宣伝行動に取り組みました。
仕事を終えて繁華街に繰り出したり、帰宅を急ぐ人々に対して25秋年闘争ビラを配布しながら、宣伝カーの上から各組合の代表が訴えました。70人が参加しました。
誰もが安心して暮らしつづけられる地域を
公務部会の檀原毅也代表委員は、公務労働者にとどまらず民間を含めた約900万人に影響する給与法の早期改正を訴えつつ、「高市首相がねらう労働時間の規制緩和に反対する。労働時間の短縮でプライベートな時間も充実できる政治を実現しよう」と呼びかけました。
全労連民間部会から駆けつけた生協労連の渡辺利賀書記次長は、「例年10月に統一して改定されていた地域最低賃金が、秋田や群馬では来年3月に先送りされ、他にも越年する県が複数ある。最賃の値切りとも言える。全国一律の最低賃金を求める」と訴えました。
自治労連の内田中央執行委員は、「高市連立政権は、維新の会が要求する医療費4兆円削減を丸呑みした。怪我や病気になったとき速やかに医療を受けられる体制が不可欠だ。医療費削減に反対する」とのべ、日本医労連の桜井中央執行委員は、「医療、介護、福祉の現場では人手不足、過重労働が蔓延している。社会的役割に見合う賃上げのためには診療報酬引き上げが必要不可欠だ。社会保障の充実、大幅増員、大幅賃上げの世論をつくり盛り上げていきたい」と決意を表明しました。
福祉保育労の仲野書記長もケア労働者の処遇改善を訴え、「介護職員と全産業とでは6~7万円の賃金差がある。その理由として、国が決めた介護報酬が非常に低いことが挙げられる。人手不足が深刻になっているなか、ケア労働者の大幅賃上げを」とのべ、国公労連・国土交通労組の泉川中央執行委員は、埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故を例にあげ、「住民の命と生活を支えるインフラを行政の責任で管理していくため、予算と要員の確保が必要だ」と訴えました。
郵政ユニオンの日巻中央執行委員長は、日本郵便で働く非正規社員と正社員との処遇の格差解消へ裁判でたたかい、最高裁で勝利判決を勝ち取った経験をのべつつ、非正規社員の賃金とも連動する最低賃金の引き上げを求めました。
最後にマイクを持った全教の山元書記次長は、「教員の給特法は改定されても、長時間過密労働も定額働かせ放題も解消できない。一方で、労働者と使用者の合意で長時間労働を可能にする仕組みが狙われている。みんなで声をあげよう」と呼びかけました。
以 上
[...] Read more...
2025年10月1日誰もが安心してくらせる社会の実現へ
=全労連公務部会第35回・公務労組連絡会第69回定期総会を開催=
全労連公務部会・公務労組連絡会は10月1日、都内で定期総会を開催し、次年度の運動方針と役員体制を確立しました。
総会には加盟単産の代議員21名と地方組織から19名、役員などを含めて72名が参加。討論では、5単産・10地方組織の16名から発言があり、運動方針を豊かに補強しました。
あらゆる分断を団結の力で跳ね返そう
全労連公務部会の日巻直映代表委員(郵政ユニオン委員長)が開会あいさつし、議長団には内田みどり(自治労連)と森川息吹(国公労連)の両代議員を選出しました。
主催者あいさつに立った桜井眞吾代表委員・公務労組連絡会議長(自治労連委員長)は、「7月の参議院選挙後、2ヶ月以上の政治空白の間も国民生活は悪化をし続けている。選挙で大敗しても自民党は裏金などの反省もない。国際的な分断の流れが日本でも生まれている。分断に団結で対抗するために、本総会を職場と地域で団結をひろげる大きなきっかけにしてほしい」と呼びかけました。
総会には、来賓として全労連から清岡弘一副議長、全労連民間部会から廣瀬肇建交労書記長、日本共産党塩川鉄也衆議院議員が駆けつけ、連帯と激励のあいさつを受けました。その後、香月直之事務局長が向こう1年間の運動方針案をはじめとした議案を提案、西芳紀事務局次長が「鳥取方式短時間勤務制度」にかかわる現地調査の報告をしました。
その後の各単産・地方組織による討論(別掲)を受けて、香月直之事務局長が総括答弁に立ち、政治を転換するチャンスが生まれているなかで、公務労働者の要求実現に向けて奮闘する決意を表明しました。提案された各議案は拍手で採決され、最後に総会宣言(別掲)を採択してすべての議事が終了しました。
総会の締めくくりに浅野龍一代表委員(国公労連委員長)が閉会あいさつし、檀原毅也代表委員(全教委員長)の発声による団結ガンバロー三唱で今後1年間を意気高くたたかう決意を固めあい、定期総会は閉幕しました。
■討論(要旨)
○ 国公労連・関口中執
今年の人事院勧告は比較企業規模の引き上げがあったが、本府省と地方との機関間格差の拡大は到底容認できるものではない。非常勤職員と常勤職員との格差は、女性に対する間接差別とも言える。均等待遇・ 均衡待遇を一刻も早く実現させる決意だ。
○ 全教・金井書記長
労基法の原則を踏みにじる給特法改定が強行された。現場の声を聞かず、授業準備や学校行事などの切り捨てで時短しようとしている。たたかいの舞台は今後各自治体になり、条例化を許さない取り組みを強めていく。
○ 自治労連・嶋林中執
賃金講座を月1回の頻度で開いている。賃金制度を語れる役員を増やし、学習を広めていく流れが生まれてきている。非正規職員の実態調査で、公募要件の撤廃が自治体では進んでいないことが明らかとなった。雇用が守る取り組みをすすめる。
○ 長野県公務労組連絡会
寒冷地手当改善を求めて、2月に県議会が全会一致で意見書を採択。7月には全県を寒冷地手当の支給対象とする、異例の人事委員会勧告が出された。強く要求してきた反映であり、大きな成果に運動への確信を感じている。
○ 埼玉公務共闘
地域手当の格差解消求め、地元選出国会議員に要請。24年人事院勧告で県内の手当無支給の地域はなくなったが、依然として自治体間の格差は解消されてない。最低生計費は大都市も地方もほぼ同じ。将来的には地域手当の廃止を求めていく。
○ 高知県公務労組連絡会
高知県知事は9月、一般行政事務を含めた「短時間勤務職員」採用枠の新設や、時間外勤務手当の割増率を25%から50%へ引き上げる方針を発表した。時間外勤務手当の引き上げについて人事委員会は、管理職の意識を変え時間外の抑制に繋げるとしている。
○ 北海道公務共闘
北海道人事委員会と2度の交渉に取り組んだ。給特法の改定について重点を置いて追及し、国会で採択された付帯決議で、人事委員会が対応するとなっていることを一つずつ確認してきた。形式的な回答ばかりで、引き続き追及していく。
○ 富山県公務共闘(準備会)
富山県内の地域手当は富山市が3%で他は無支給だ。県内一律の地域手当を求めて、日教組や自治労傘下の組合とも共同して、県人事委員会委員長と教育長あての統一署名に4年ぶりに取り組んだ。なんとしても成果を出したい。
○ 千葉県公務労組連絡会
25人勧では、地域最低賃金を下回った場合は補填する手当支給が勧告された。これまで自治体当局や人事委員会は、公務員は最低賃金法の適用外であると回答してきた。公務員も最賃を下回ってはいけないと認めさせた意義のある勧告だ。
○ 郵政ユニオン・谷川中執
非正規社員の寒冷地手当支給を求めた集団訴訟で、東日本訴訟に続いて北海道訴訟でも最高裁が控訴棄却の不当判決を出した。正社員との格差を司法が是認したもので、とうてい納得できない。引き続き格差是正を求めてたたかっていく決意だ。
○ 日本医労連・櫻井中執
25春闘では5万円以上の賃上げ要求を掲げ、全国の仲間がストに決起してたたかう姿を社会に示した。診療報酬の臨時改定を求める署名には多くの賛同が寄せられた。秋闘は「ケア労働者の大幅賃上げアクション」で奮闘する。
○ 自治労連・吉田書記次長
医療や介護で働くケア労働者の処遇改善は、自治体職場の重要な課題となっている。ケア労働者の賃金や労働条件の問題は、地域住民の命と暮らしに深く関わっており、公共を取り戻す運動と一体で進めていくことが重要だ。
○ 滋賀公務共闘
近畿公務共闘として、人事院近畿事務局と3回交渉をしてきた。特に交通用具利用者の通勤手当引き上げを重点に追及した。滋賀公務共闘としては、9月に学習会を実施した。香月事務局長を講師に招き、地方公務員の確定闘争へたたかう決意を固めた。
○ 大阪公務共闘
大阪公務共闘と大阪労連民間部会は人事院近畿事務局への要請行動に取り組み、官民の共同を実感することができた。8月の人事院勧告の翌日には、合同庁舎前で大阪国公が開催した緊急抗議集会に連帯して結集した。
○ 山口県公務共闘
山口では地域手当が県内の全市町が0%となっている。市町村会への要請行動を通して、県内のどの自治体も人口流出に強い危機感を持っていることがわかった。地域手当は公務労働者だけではなく地域全体の課題だ。
○ 佐賀県公務労組連絡会
給与制度のアップデートによって、行政職と教育職の格差が大きくなるのではないかと懸念している。行政職と高校教員では昇格スピードに大きな格差があり、高校の場合は2級で採用されて2級のまま定年を迎える職員が9割を超えている。
以 上 総 会 宣 言
私たちは、全労連公務部会第35回定期総会および公務労組連絡会第69回定期総会を開催し、この一年間の闘いを総括するとともに、2025年度運動方針を確立した。総会では、憲法尊重・擁護の義務を負う公務労働者として、憲法改悪・大軍拡を許さず、国民犠牲の政治を転換させるため、全国の職場と地域から全力で闘う決意を固めた。
この間、新自由主義による公共部門の再編・統廃合、民営化・業者委託化、非正規化、人員削減が進められ、日本の公務員数は世界最低水準となっている。こうした公務・公共サービスの無差別な削減の弊害が、頻発する大規模災害や事故で露呈し、公務労働者の存在と役割が再認識された。しかし、政府はこうした実態を無視し、デジタルトランスフォーメーション(DX)や官民連携を推進して、さらなる人員削減と公的サービスの縮小を狙っている。私たちは、公務労働者・労働組合としての役割を存分に発揮し、「公共を取り戻す」運動を住民とともに進め、政府の総人件費抑制方針を転換させ、公務・公共サービス、教育の拡充を実現する。
今年の人事院勧告は、34年ぶりに改定率が3%を超えた。俸給表については、若年層に重点を置きつつ、全ての級・号俸で2.7%以上の引き上げを実現させた。しかし、賃金改善は25年春闘平均引上げ率にも満たず、生活改善を実感できる水準からは程遠い。また、「最終提言」を金科玉条とし、キャリア官僚優遇、裁量労働制の導入、いわゆる「ジョブ型」給与への移行などを期限を切って急ぐ人事院の姿勢は、労働基本権制約の「代償機関」とは到底言えない。人事院勧告の制度疲労は明らかであり、労働基本権の回復は喫緊の課題である。引き続き、政府への追及を強めるとともに、国内外の世論に訴える取り組みを旺盛に展開していく。
いま私たちは、戦争か平和か、急激な少子化、広がる貧困と格差の拡大、気候危機など、さまざまな困難と課題に直面している。職場に目を向けると、深刻な人手不足、能力・実績主義の強化、長時間過密労働が横行し、医療・介護・福祉の職場で働く労働者の低賃金構造も放置されたままだ。その根本には、「財界・大企業優遇」「アメリカいいなり」の自公政権とその補完勢力の政治姿勢がある。
加えて、7月の参院選挙で外国人差別を声高に主張する極右・排外主義の勢力が伸長し、政治の逆行が懸念されている。「スパイ防止」の名の下で公務労働者と国民の監視を強め、取り締まろうとする危険な動きも強まっている。
こうした状況を打開するため、国民・住民が主人公の政治への転換は避けて通れない。職場の切実な要求実現のため、何としても自民党政治の抜本的転換を果たそう。
全労連公務部会・公務労組連絡会は、この間の運動の成果を確信に、大軍拡・憲法改悪阻止、公務・公共サービスと教育の拡充、ジェンダー平等など、誰もが安心してくらせる社会の実現に向け、職場・地域から全力を挙げて奮闘するものである。
以上、宣言する。
2025年10月1日
全労連公務部会第35回・公務労組連絡会第69回定期総会 [...] Read more...
2025年9月18日賃金・労働条件めぐって使用者責任を追及
= 人勧の取り扱いで内閣人事局と中間交渉 =
公務労組連絡会は9月18日、人事院勧告直後に提出した「公務員賃金等に関する要求書」の実現を求めて、政府・内閣人事局と中間回答交渉を行いました。
交渉には、公務労組連絡会からは桜井議長を先頭に、檀原副議長、香月事務局長以下幹事会5名が参加、内閣人事局は次田総括参事官補佐ほかが対応しました。
「必要な分野は増員している」と強弁
交渉にあたって桜井議長は、「人事院勧告は、民間の賃上げや最賃引き上げ率とくらべても不満が残る内容となった。とりわけ臨時・非常勤職員の処遇改善はゼロ回答で、使用者として改善にむけた努力を求める」とのべ、現在、検討中の内容について質しました。
これに対して次田総括参事官補佐は、要求書の各項目に沿って中間的な回答を示しました。
【内閣人事局・中間回答】
1、賃金の改善等について
本年の給与の取扱いについては、去る8月7日に人事院から国家公務員の給与についての報告及び勧告があったことを受け、同日、第1回の給与関係閣僚会議が持ち回りで開催されたところ。同会議においては、人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立って、国政全般の観点から給与関係閣僚会議において検討を進め、早急に結論を出す必要がある旨、確認されたところである。今後、適切な時期に改めて給与関係閣僚会議が開催されることとなっている。
2、非常勤職員の処遇改善について
国家公務員の場合、
・非常勤職員の官職は、常勤の官職とは、業務の性質や職務の内容が異なるものであること
・また、非常勤職員を任期の定めのない常勤職員の官職に任用するためには、国家公務員法に基づき、採用試験などにより、常勤職員としての能力の実証を行う必要があること
から非常勤職員の常勤化・定員化や任期の定めのない非常勤職員の任用は困難であることを御理解いただきたい。
なお、非常勤職員についても、公開・平等の採用試験など常勤職員としての能力の実証を行う手続に応募する機会は広く与えられており、こうした手続を経て常勤職員として採用されることはあり得るものと考えている。
非常勤職員の処遇改善に係る取組として、まず、給与については、人事院において、常勤職員との均衡をより一層確保することを目的として、一昨年4月に非常勤職員の給与に関する指針を改正し、給与法等の改正により常勤職員の給与が改定された場合には、非常勤職員の給与についても、常勤職員に準じて改定するよう努める旨を追加し、この指針に沿った適切な給与支給が行われるよう、各府省を指導していくものと承知している。なお、給与の遡及改定については、昨年12月に人事院と内閣人事局から改めて周知を図ったところ。
非常勤職員の休暇等 については、人事院において検討されるべきものと承知しているが、令和7年4月に子の看護等休暇の利用対象拡大や病気休暇の有給化といった制度改正が行われるなど、着実に制度の整備を進めてきているところ。
3、60歳を超える職員の賃金について
60歳を超える職員の給与については、令和3年に成立した「国家公務員法等の一部を改正する法律」において、人事院の意見の申出に基づき、60歳を超える職員の俸給月額は、当分の間、60歳時点の俸給月額の7割とされたもの。
なお60歳前・60歳超の各職員層の給与水準(給与カーブ)の在り方については、令和5年8月の人事院勧告時の報告において、段階的に定年が引き上げられる中での公務における人事管理の在り方の変化や、民間における高齢期雇用や高齢層従業員の給与水準の状況を注視しつつ、職員の役割・貢献に応じた処遇の確保の観点から、人事管理に係る他の制度と一体で引き続き検討を行っていくこととされており、政府としても、人事院における所要の検討の内容を踏まえ、適切に対応してまいりたい 。
4、再任用職員について
給与水準や諸手当の措置は、今後の職務・働き方の実情や民間の給与実態等を踏まえて人事院において検討されるべきものと考える。政府は平成25年3月の閣議決定で人事院へ 給与制度上の措置についての検討を要請し、これに対し平成29年8月の人事院勧告時の報告では再任用職員の給与について、民間企業の再雇用者の給与の動向、各府省における再任用制度の運用状況等を踏まえつつ、引き続き、その在り方について必要な検討を行っていくこととされている。
こうした中で、昨年の人事院勧告に基づき、給与法改正により再任用職員に対し新たに住居手当や特地勤務手当等の支給を可能とする制度改正を行ったところ。引き続き 内閣人事局としては人事院における所要の検討を踏まえ、適切に対応してまいりたい。
また、「国家公務員の定年引上げに向けた取組指針」では定年の段階的な引上げ期間中に、定年退職者が再任用を希望する場合には、平成25年3月の閣議決定に準じて、当該職員を公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、再任用するものとしていることを踏まえ、各任命権者を含め、政府全体で適切に対応してまいりたい 。
5、客観的な勤務時間管理・長時間労働の是正について
超過勤務の縮減のため、各府省等は、「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」等に基づき、 業務の廃止・効率化、デジタル化、マネジメント改革推進のための取組等を進めている。
今後とも、勤務時間などの基準を定めている人事院と連携して超過勤務の縮減に取り組んでまいりたい。なお、勤務時間管理に関しては、本年8月の「公務員人事管理に関する報告」でも言及されているが、人事院、デジタル庁と連携して、令和8年度までに勤務時間管理共通システムの基本機能を整備することとしている。
これらのデジタル化の推進により、客観的な方法により取得したデータの活用や、部下の超過勤務や勤務間インターバルの確保の状況等の勤務時間の見える化を実現し、上司による適正なマネジメントを促進してまいりたい 。
定員管理については、国民のニーズを踏まえて、新たな行政需要に的確に対応していくためには、既存の業務を不断に見直し、定員の再配置を推進していくことが重要である。その上で、新たな行政課題や既存業務の増大に対応するため、各府省官房等から現場の実情を聴取しつつ必要な行政分野に必要な増員を行っているところ。引き続き、既存業務の見直しに積極的に取り組みながら、内閣の重要政策に適切に対応できる体制の構築を図ってまいりたい。
6、両立支援について
両立支援に係る休暇・休業等の国家公務員の勤務条件については、一義的には人事院において検討されるべきものと認識している。いずれにしても、男性の育児休業の取得推進など、男女問わず仕事と生活の両立支援を推進するとともに、フレックスタイムを活用するなどの柔軟な働き方の推進等、働きやすい職場環境の整備についても取組を進めてまいりたい。
7、労働基本権について
自律的労使関係制度については、多岐にわたる課題があると認識しており、皆様と誠実に意見交換しつつ、これからも更に意思疎通を深めてまいりたいと考えている。
常勤的な非常勤職員は無期雇用せよ
これに対して、公務労組連絡会側は主に以下の点を追及しました。
○ 物価高騰のもとで、4%にも満たない賃上げ勧告では生活改善には不十分だ。しかも、中高年層職員は改定率が逓減された。勧告尊重にとどまるのではなく、経済対策としての側面からも、使用者として勧告にとどまらない賃金改善を求める。
○ 非常勤職員の処遇改善を強く求める。本日の回答では、常勤職員と業務の性質や職務の内容が異なるとして、非常勤職員の無期雇用化や常勤化を拒否したが、ならば、常勤職員と同様の業務を命じられている非常勤職員を、常勤化できない理由はなくなる。ただちに常勤化せよ。
○ 超過勤務の縮減の方策が縷々のべられたが、増員なくして長時間労働の根本的解消につながらないのは自明の理だ。小手先の改善策ではなく、使用者・政府として大幅な増員へ努力せよ。
その他、高齢者雇用、性別による賃金格差の解消、労働基本権の回復などにかかわって、各単産の現状も示しながら、要求の実現を求めました。
これに対して内閣人事局側は、「非常勤職員の任用については、人事院が昨年11月に作成した『期間業務職員の採用等に関するQ&A』も踏まえつつ、引き続き適切に対応していく。常勤化は、能力の実証が必要となることから困難だ」「要員配置は、現場の実情を聴取しつつ必要な行政分野に必要な増員を行っている」とのべ、労働基本権回復をめぐっては、「労働組合とも誠実に意見交換しつつ、これからも更に意思疎通を深めていきたい」と従来通りの回答を繰り返しました。
最後に桜井議長は、「鳥取県が人材確保を目的に独自の制度を創設したり、高知県では時間外勤務手当の引き上げが条例として議論されるなど、地方自治体で新たな動きが見られる。内閣人事局としても、公務労働者の生活と権利を守るために、使用者としての責任を果たせ」とのべ、諸要求の実現へ最終回答にむけてさらなる検討を求めて交渉を終えました。
以 上 [...] Read more...
2025年8月29日全国の自治体で働く職員の労苦に応えよ
= 人事院勧告をうけて全人連に要請 =
公務労組連絡会は8月8日、全人連(全国人事委員会連合会)に「地方人事委員会の勧告に関する要請書」を提出し、前日に出された人事院勧告を踏まえつつ、自治体職員、教職員の賃金・労働条件の改善にむけて、各地の人事委員会が積極的な役割を果たすよう求めました。
要請には、公務労組連絡会の香月直之事務局長、自治労連の橋口剛典書記長、全教の金井裕子書記長らが参加、全人連は丸山雅代事務局長が対応しました。
要請にあたって香月事務局長は、「全国の自治体では、地方財政がきびしいなかでも、第一線で働く公務労働者は、臨時・非常勤職員をふくめて、住民の期待に応えるために日夜奮闘している。こうした労苦に応えるため、本日提出した要請書に沿って尽力いただきたい」と求めました。
丸山事務局長は、「要請は確かに承った。早速、全国の人事委員会に伝えたい」とのべました。また、8月29日には中西充会長名の回答が、以下の通り文書にて届けられました。 【中西充全人連会長からの回答】
8月8日の要請につきましては、早速、全国の人事委員会にお伝えしたところです。
今年の人事院勧告では、官民給与の比較方法について、比較対象企業規模を 50 人以上から100人以上に引き上げる等の見直しが行われました。
本年の官民較差は、比較方法の見直しと、民間企業の賃上げの状況等を反映して、民間給与が公務員給与を額にして 15,014 円、率にして3.62%上回っており、この較差を解消するため、月例給は、初任給を大幅に引き上げ、若年層に重点を置きつつも、その他の職員についても昨年を大幅に上回る引上げ改定を行うこととしております。
特別給につきましても、年間の平均支給月数を 0.05 月分引き上げ、4.65 月分とすることとしております。
また、手当に関しては、特地勤務手当等について他の手当との調整措置を廃止するほか、自動車等使用者に対する通勤手当の見直し等を行うこととしております。
公務員人事管理に関する報告においては、優秀な人材の確保のための新たな人事制度、ライフスタイルや働き方に対する価値観の多様化に応じた勤務環境の整備の必要性等について言及されております。
国家公務員と地方公務員の立場の違いはありつつも、人事院の勧告は、各人事委員会が勧告作業を進めていく上で参考になるものであることから、その内容は十分に吟味する必要があります。
今後、各人事委員会は、中立かつ公正な人事行政の専門機関として、皆様からの要請の趣旨も考慮しながら、それぞれの実情等を勘案し、主体性をもって対処していくことになるものと考えております。
全人連といたしましても、引続き各人事委員会の主体的な取組を支援するとともに、人事院、各人事委員会との意見交換に十分努めてまいります。
以 上
(添付資料)(PDFファイル)
全人連に提出した要請書 [...] Read more...
2025年8月26日勧告の枠にとどまらない賃上げを
= 人事院勧告直後に各省大臣に要求書提出 =
人事院勧告が出された翌日の8月8日、公務労組連絡会は政府・内閣人事局に「公務員賃金等に関する要求書」を提出し、勧告の取り扱いをめぐって交渉しました。
交渉には、公務労組連絡会の桜井議長を先頭に、香月事務局長以下幹事会5名が参加、内閣人事局は次田総括参事官補佐ほかが対応しました。
この日は厚生労働省・総務省・財務省に対しても同趣旨の要求書を提出、公務労働者の賃金・労働条件の改善を求めました。
使用者として現場の労苦に応えよ
内閣人事局との交渉で桜井議長は、「政府は、勧告の範囲でとどまるのではなく、異常な物価高から生活を守り、第一線現場を支えている多くの職員の労苦に応えるため、大幅な賃金改善を図るべきだ」とのべました。
交渉団は、積極的な賃金引き上げをはじめ、勧告で触れられなかった非常勤職員の処遇改善、長時間労働の解消にむけた増員などを強く求めました。
これに対して、内閣人事局側は次のように回答しました。
● 昨日、人事院から給与改定に関する勧告が提出されました。これを受けて、その取扱いの検討に着手したところです。
● 国家公務員の給与については、国家公務員の労働基本権制約の代償措置である人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立ち、国政全般の観点から、その取扱いの検討を進めてまいります。
その過程においては、皆様方の意見も十分にお聞きしたいと考えています。
● 給与以外の要求事項についても、しかるべき時期に回答を行いたいと考えております。
以上の回答を受け、桜井議長から勧告の取り扱いに関わっては引き続く交渉・協議を求め、勧告直後の交渉を終えました。
給与関係大臣の役割を果たせ
厚生労働大臣に対する要求書提出は、香月事務局長、西、山元の各事務局次長ほかが参加、厚生労働省は大塚労使関係参事官ほかが対応しました。大塚参事官は、「公務志望者を確保するために、賃金面だけではなく働きやすい職場環境を含めた整備が必要だ」とのべ、香月事務局長は、「給与関係閣僚会議の一員として、要求書の実現に向けて積極的な役割を果たしてもらいたい」と求めました。
財務大臣あての要求書提出は、主計局の藤田給与共済課補佐ほかが対応しました。藤田課長補佐は、「財務省としては、人勧制度を尊重することが基本姿勢だ。今後、国民の理解を得られるよう各省と議論を進めていきたい」とのべました。
総務大臣への要請書の提出は、公務労組連絡会から西、山元の各事務局次長、自治労連から嶋林中執が参加、総務省は自治行政局公務員課の課長補佐ら7名が対応しました。
以 上
(添付資料)(PDFファイル)
(1) 政府・内閣人事局あての要求書
(2) 財務大臣あての要求書
(3) 厚生労働大臣あての要求書
(4) 総務大臣あての要請書 [...] Read more...
2025年8月5日3.6%台のベア、本府省をあからさまに優遇
= 「夏季重点要求」に対して人事院が最終回答 =
公務労組連絡会は8月5日、「25年夏季重点要求」をめぐって人事院との最終交渉に臨みました。人事院側は「3.6%台前半」の官民較差にもとづいて、俸給表全般にわたる賃上げを実施、0.05月分の一時金引き上げを8月7日に勧告したいと回答しました。
交渉には、公務労組連絡会から檀原副議長を先頭に5人が参加、人事院は黒木給与第一課課長補佐と佐藤職員福祉課課長補佐が対応しました。
なお、交渉に先立って、「公務労働者の大幅賃上げ等を求める署名」2,100人分を追加提出、累計では80,843人分となりました。
最賃にも届かない職員に差額支給で対応
檀原副議長が、夏季要求に対する最終回答を求めたことに対して、人事院側は以下の通り回答しました。
【人事院最終回答(要旨)】
(給与改定について)
勧告日は、8月7日木曜日となる予定である。
既に報道発表したが、本年の勧告にあたっては、人事行政諮問会議の最終提言も踏まえ、官民給与の比較方法の見直しを行う。行政課題の複雑化・多様化や今日の厳しい人材獲得競争を前提にすれば、公務の職務・職責を重視するとともに、より規模の大きい企業と比較する必要があることから、比較対象とする企業規模を「50人以上」から「100人以上」とし、本府省と対応させる企業規模を東京23区本店「500人以上」から「1,000人以上」とした。
月例給の民間給与との較差は、民間企業の賃上げの状況を反映して、3.6%台前半の引上げとなる見込みである。
特別給は、0.05月分の引上げとなる見込みである。引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分し、令和7年度については、12月期の期末手当及び勤勉手当に配分する。令和8年度以降は、6月期及び12月期が均等になるよう配分する。
俸給表の改定は、行政職俸給表(一)について、民間における初任給の動向や、公務において人材確保が喫緊の課題であること等を踏まえ、総合職試験(大卒程度)及び一般職試験(大卒程度)に係る初任給を12,000円、一般職試験(高卒者)に係る初任給を12,300円引き上げることとする。これを踏まえ、おおむね30歳台後半までの職員が在職する号俸に重点を置いた引上げ改定を行うとともに、その他の職員が在職する号俸については、改定率を逓減させつつも、昨年を上回る引上げ改定を行う。
その他の俸給表については、行政職俸給表(一)との均衡を基本に所要の引上げ改定を行う。定年前再任用短時間勤務職員の基準俸給月額は、各級の改定額を踏まえ、所要の引上げ改定を行う。
自動車等使用者に対する通勤手当について、本年の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえ、自動車等により通勤することが必要な職員の負担に配慮して、令和8年4月から、距離区分の上限を「100km以上」とし、「60km以上」の部分について5km刻みで新たな距離区分を設け、その上限額は66,400円とする。また、現行の「60km以上」までの距離区分についても、200円から7,100円までの幅で引上げ改定を行い、令和7年4月に遡及して実施する。
また、1か月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を令和8年4月より新設する。なお、職員に対して適時適切に通勤手当を支給するため、月の途中で採用された職員等に対し、採用日等から通勤手当を支給できるよう所要の措置を講じ、令和8年10月から実施する。
人材獲得競争が激しくなる中、最低賃金の上昇が続いていることを踏まえ、職員の月例給与水準を適切に確保するための措置として、令和8年4月以降、月例給与の水準が地域別最低賃金に相当する額を下回る場合に、その差額を補填するための手当を支給することとする。
(「新たな人事制度」の構築に向けた先行的見直しについて)
人事院では、人事行政諮問会議の最終提言も踏まえた新たな人事制度の構築に向けて検討を進めているが、職務・職責を重視した給与を実現し、公務にとって必要不可欠な転勤をする職員に対する給与上の課題に速やかに対処する観点から、先ほど言及した官民給与の比較対象の見直しのほかにも、先行して見直しを行うものがある。
まず、本府省の業務の特殊性・困難性の高まりに伴い、本府省の職員の職務・職責が重くなっていることを踏まえ、本府省業務調整手当の支給対象に本府省の幹部・管理職員を加え、51,800円を支給するほか、本府省の課長補佐級職員の手当額を10,000円、係長級以下の職員の手当額を2,000円引き上げる。なお、この改定は、官民給与の比較における本府省部分の対応関係の見直しにより生じた較差の範囲内で行い、対応関係の見直しにより生じる較差の一部は、俸給表の改定に用いることとする。
また、職務給の原則の下、職務・職責に見合った給与処遇が確保できるよう、職員が昇格するために原則として一定の期間昇格前の級に在級することを求める在級期間に係る制度を廃止する。
さらに、異動の円滑化を図るため、著しく不便な地に所在する官署に勤務する職員に支給される特地勤務手当等と他の手当との減額調整措置を廃止するとともに、特地官署等への採用に伴い転居を行った職員には、特地勤務手当に準ずる手当を新たに支給することとする。
(勤務環境の整備について)
過重な超過勤務は、職員の心身の健康を損ない、組織の活力を低下させるものであり、職員のWell-beingや「選ばれる」公務職場を実現するためにも、超過勤務の縮減が最重要課題である。長時間労働の是正、とりわけ月100時間などの上限を超える超過勤務の最小化に向けて、不退転の決意で取組を進める。
具体的には、個々の職場の実情をくみ取った縮減策を示し、その着実な実施を伴走支援していくほか、超過勤務時間の適正な管理や長時間の超過勤務の縮減に関する調査・指導を行っても取組が不十分な場合は、新たに実施する臨時調査などでより一層の取組と改善状況の報告を求めていく。また、上限を超えて超過勤務をすることができる特例業務の範囲に関する判断を厳格にするよう各府省への指導を強化する。
さらに、各府省の実情を把握できるデータや各府省からの改善要望等を関係部局に示し、各府省の柔軟な要員確保が進むよう支援していくとともに、行政部内を超えた取組が必要と判断されるものについては、国会を始めとする関係各方面のご協力もお願いしていく。
また、柔軟な働き方を整備するため、自己実現や社会貢献につながるような自営兼業を可能とする見直しを行うほか、昨年の公務員人事管理に関する報告において言及した、育児や介護などに限らない職員の様々な事情に応じた無給の休暇の新設等について具体的な検討を進める。
一人一人の職員が生き生きと働き、パフォーマンスを最大限に発揮できるよう、Well-beingの土台となる職場環境を整備していくことは、引き続き急務である。このため、勤務間のインターバル確保や職員の健康増進に向けた健康管理、ゼロ・ハラスメントの実現に向けた取組としてカスタマー・ハラスメントへの対策も進める。
今後とも、職務・職責をより重視した給与体系を含む、新たな人事制度の構築に向けて、職員団体の意見も伺いながら、検討を進める。
全職員対象に比較企業規模を1,000人にせよ
人事院の最終回答を受けて檀原副議長は、「3%台の賃上げは、この間の物価上昇分をも下回るもので、生活改善には極めて不十分な水準でしかない」とのべ、交渉団は主に以下の点を追及しました。
○ 民間の春闘結果や最賃目安額の改善率6%ともかけ離れている。なぜそんな勧告になるのか。比較対象企業規模を「50人以上」から「100人以上」に戻したというが、民間相場に公務員賃金が追い付くことは制度的に困難なことが明らかになった。すべての職員を対象にして、比較企業規模を1,000人以上に引き上げることを求める。
○ とりわけ問題なのは、本府省業務調整手当の対象拡大を通して、本府省と地方の賃金格差をさらに拡大させようとしていることだ。地方の第一線で働く職員の誇りを傷つけ、士気の低下を招くことなどからも認められない。官民較差の改善で生じた原資は、一部の職員だけに限定することなく、年代や地域など、あらゆる格差を解消するために配分せよ。
○ 繰り返し要求してきた非常勤職員の処遇改善には何ら言及がなかった。非正規公務員の正規職員化、「任期の定めのない短時間勤務公務員制度」の創設など、雇用不安を根本からなくすべきだ。また、依然として休暇制度等に常勤職員との不合理な格差があり、改善を重ねて求める。
最後に檀原副議長は、「本日の回答は不満だ。引き続き、われわれの声を受け止めよ」とのべ、交渉を終えました。
以 上 [...] Read more...
2025年7月25日勧告せまるなか人事院に生の声をぶつける
= 猛暑を跳ね返して夏季中央行動で奮闘 =
公務労組連絡会・全労連公務部会は7月25日、「25人勧闘争勝利!中央行動」に取り組み、公務員賃金の大幅引き上げ、地域間格差の是正、再任用・非正規職員の処遇改善と雇用の安定などを求めて、人事院前要求行動や学習総決起集会で奮闘しました。
気温が35度を超える猛暑のなか、全国から500人の仲間が横断幕やプラスターボードを掲げて結集、全労連・国民春闘共闘規模でとりくんだ「公務労働者の大幅賃上げなどを求める署名」を人事院に提出しました。
人事院前要求行動
生活改善が実感できる大幅賃上げ勧告を
全労連規模で取り組んだ人事院前の要求行動で、主催者あいさつした秋山全労連議長は、「人事院はこれまでの賃金政策を転換せよ。初任給の引き上げとともに、中高年層の賃金改善を求める」とのべ、全労連公務部会の香月事務局長が、目前に迫った人事院勧告をめぐるたたかいの重点を報告、「切実な要求を職場の対話でひろげて、仲間を増やし一緒に声をあげていこう」と呼びかけました。
これを受けて、生協労連の岩城副委員長、東京自治労連の岩間副委員長、大阪教職員組合の山下副委員長、愛知国公の柴田副議長、山口公務共闘会議の河野副委員長が決意表明し、郵政ユニオンの青柳中央執行委員のシュプレヒコールで人事院前要求行動を締めくくりました。
行動後に人事院へ署名提出行動に取り組み、全労連の九後副議長、公務労組連絡会の西事務局次長を先頭に、東京自治労連、大阪教職員組合、愛知国公、山口公務共闘会議の各代表が参加し、78,743人分の署名を提出するとともに要求の実現を訴えました。人事院は中山博之連絡調査官が対応しました。
学習決起集会
最後までねばり強くたたかう決意を固め合う
14時過ぎからは国会議事堂近くの星陵会館で学習総決起集会を開催、公務労組連絡会の大門事務局次長の司会進行のもと、主催者あいさつで公務部会の桜井代表委員は、「参議院選挙では自民・公明党が過半数に追い込んだ。一方では改憲勢力が増え、憲法遵守の義務を負う公務労働者の役割はいっそう重要になっている。職場と地域に憲法がいきる社会にするために、すべての仲間と一緒に夏季闘争、秋季闘争にむけて奮闘しよう」と呼びかけました。
その後、香月事務局長による情勢報告を通して、賃金や労働条件をめぐる今年の人事院勧告の焦点をはじめ、公務労働者の労働基本権回復にかかわって学習を深めました。報告を受けて、自治労連の橋口書記長、全教の金井書記長、国公労連の笠松書記長の3人が登壇し、各単産の課題や要求を踏まえつつ、人事院勧告にむけてたたかう決意を力強く表明しました。
浅野代表委員が閉会あいさつし、最後に檀原代表委員の発声で団結がんばろうを三唱、学習決起集会を締めくくりました。
以 上 [...] Read more...
2025年7月24日使用者責任が見られない不満な回答
= 夏季重点要求で内閣人事局と最終交渉 =
公務労組連絡会は7月24日、「2025年夏季重点要求書」に対する最終交渉を行いました。
交渉には、公務労組連絡会の桜井議長を先頭に、檀原副議長、香月事務局長以下幹事会6名が参加、内閣人事局・次田亜美総括参事官補佐ほかが対応しました。
賃上げも非常勤職員の処遇改善も人事院まかせ
交渉の冒頭、桜井議長が「中間交渉の際、回答は不満であり、さらなる検討を行うよう求めてきた」とのべ、最終回答を求めました。
次田総括参事官補佐は、以下の回答を示しました。
【内閣人事局最終回答】
「1 賃金・昇格等の改善」に関し、国家公務員の給与改定に当たっては、国家公務員の適正な処遇の確保や、国民の理解を得る観点からも、また、労働基本権制約の代償措置といった観点からも、第三者機関としての人事院が専門的見地から行った官民比較に基づく人事院勧告を尊重することが政府としての基本姿勢である。
今後も、諸情勢を踏まえつつ、対応していく。
「2 非常勤職員制度の抜本改善」に関し、非常勤職員の任用については、例えば期間業務職員に関して、人事院において、各府省や職員団体の意見等も踏まえながら、制度官庁と協議をした上、各府省における円滑な運用に資するよう「期間業務職員の採用等に関するQ&A」を昨年11月に作成したと承知している。これを踏まえ、内閣人事局としては、昨年11月に各府省に対し、期間業務職員の再採用に当たって適切に運用を行うよう周知を行ったところであり、引き続き各府省の運用を注視しつつ、必要に応じて適切な対応を検討してまいりたい。
非常勤職員の給与については、人事院において、常勤職員との均衡をより一層確保することを目的として、一昨年4月に非常勤職員の給与に関する指針を改正し、給与法等の改正により常勤職員の給与が改定された場合には、非常勤職員の給与についても、常勤職員に準じて改定するよう努める旨を追加し、この指針に沿った適切な給与支給が行われるよう、各府省を指導していくものと承知している。なお、給与の遡及改定については、昨年12月に人事院と内閣人事局から改めて周知を図ったところである。
非常勤職員制度については、非常勤職員には様々な勤務形態や類型があることから、一律に検討することは困難と考えられるが、人事院において適切な運用の在り方について検討されるものと承知しており、内閣人事局としては、人事院における検討を踏まえ、適切に対応してまいりたい。
「3 国民本位の行財政・司法の確立」に関し、定員管理については、国民のニーズを踏まえて、新たな行政需要に的確に対応していくためには、既存の業務を不断に見直し、定員の再配置を推進していくことが重要である。
その上で、新たな行政課題や既存業務の増大に対応するため、各府省官房等から現場の実情を聴取しつつ必要な行政分野に必要な増員を行っているところである。
引き続き、既存業務の見直しに積極的に取り組みながら、内閣の重要政策に適切に対応できる体制の構築を図ることとしている。
「4 高齢期雇用・定年延長」に関しては、シニア職員がその知識・経験を存分に発揮し、働き方改革等にもつながるよう、各府省等における状況や取組などに関しての府省等横断の情報共有、シニア職員の意識改革・貢献意欲向上のための研修の実施等の取組を計画的かつ着実に進めてまいりたい。
「5 民主的公務員制度と労働基本権の確立」に関して、自律的労使関係制度については、多岐にわたる課題があることから、慎重な検討が必要と考えている。皆様とは誠実に意見交換をする中で、さらに意思疎通を深めてまいりたい。
「6 労働時間短縮など働くルールの確立」に関し、超過勤務の縮減のため、各府省等は、「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」等に基づき、業務の廃止・効率化、デジタル化、マネジメント改革推進のための取組等を進めている。今後とも、勤務時間などの基準を定めている人事院と連携して超過勤務の縮減に取り組んでまいりたい。
「7 両立支援制度の拡充、男女平等・共同参画の推進」に関し、育児休業については、昨年の民間労働法制の改正により民間労働者に認められた措置に相当するものとして、国家公務員の育児休業等に関する法律を改正し、新たな選択肢を追加するなどの制度改正を行ったところである。引き続き、民間労働法制の動きを注視してまいりたい。
「8 健康・安全確保等」に関し、内閣人事局としては、各府省の取組を補完するため、パワー・ハラスメントやカスタマー・ハラスメントを含むハラスメント防止講習を提供しているところ。
引き続きハラスメントに係る研修や講演会等の啓発活動を行うとともに、カスタマー・ハラスメント対策については、各府省等における実態や取組の事例の調査を実施し、調査結果を共有すること等により、各府省の取組を支援してまいりたい。
「物価上昇を上回る賃上げ」が実現できるのか
以上の回答を受け、公務労組連絡会側は以下のような点を中心に追及しました。
○ 人勧尊重だけでは、「物価上昇を上回る賃上げの普及・定着」という政府の目標は達成できない。実質賃金のマイナスに歯止めをかけるためにも、公務員賃金の政策的な引き上げが求められている。使用者として大幅賃上げを政府は決断せよ。
○ 正規職員を大幅に削減し、非正規職員に置き換えてきた国の政策をあらためよ。正規職員の増員をはじめ、非正規から正規職員への任用替え、「任期の定めのない短時間勤務公務員制度」の創設など、非正規公務員の雇用不安を根本から解消せよ。
○ 従来の定員管理の方法をあらため、人件費総額の範囲で各省各庁の長に裁量権を与える方式にするなど、新たな考え方の導入を検討を求める。その際、定員管理は労働条件に密接に関わることから、労働組合との協議は不可欠だ。
○ 労働基本権の回復・自律的労使関係制度について、対等な労使関係の実現するうえでも、私たちが求めている労使協議の場を求める。ILOが何度も勧告してきた「社会対話」に向けて政府は一歩を踏み出せ。
桜井議長は最後に、「自民・公明の与党が参議院でも少数になり、公務を取り巻く状況も大きく変化しようとしている。そのなかで、全体の奉仕者としての公務労働者の役割が揺らぐことがあってはならない。まもなく行われる人事院勧告の取り扱いにかかわっては、あらためて要求書を提出するので、真摯な対応を求める」とのべ、夏季重点要求をめぐる交渉を閉じました。
以 上 [...] Read more...
2025年7月17日給与比較の企業規模は人材確保の観点から検討
= 夏季重点要求をめぐって人事院と中間交渉 =
公務労組連絡会は7月17日、桜井議長を先頭に「2025年夏季重点要求書」に対する人事院との中間交渉に臨みました。
人事院側は職員福祉局の佐藤職員福祉課長補佐、給与局の黒木給与第一課長補佐ほかが対応しました。
賃金改善は「何とも申し上げられない」
交渉にあたって桜井議長は、「すべての世代の大幅賃上げ、あらゆる格差の解消、非正規公務員の処遇改善など、人事院が私たちの切実な要求に応えるよう求める」とのべ、今年の人事院勧告にむけた現時点での検討状況をただしました。
これに対して、以下のような回答が示されました。
【人事院回答】
1.勧告等について
(1) 勧告作業について
今年の職種別民間給与実態調査は、4月23日から6月13日までの期間で実施したところであり、現在集計中である。
本年も労働基本権制約の代償機関として、人事院としての責務を着実に果たすよう、国家公務員の給与と民間企業の給与の精緻な調査に基づき、その精確な比較を行い、必要な勧告、報告を行いたいと考えている。
(2) 賃金の改善について
月例給与・一時金については、現在、民調結果を集計中であり、今の段階では何とも申し上げられない状況である。本年においても民調の結果に基づき、適切に対処したいと考えている。
官民給与の比較を行う際の企業規模については様々な議論があるが、国家公務員の給与は、社会的な御理解、関係各方面の御理解が得られるものであることが重要と考えている。比較対象とする企業規模の引上げは、人材確保の要請も考慮した適切な報酬水準を設定していく必要性を踏まえ、引き続き各方面の意見も伺いながら、検討を行ってまいりたい。
また、昇格の要件としての在級期間が存在することが、上位の役職段階に昇任したにもかかわらず、職務の級がそれまでの役職段階のままであるといった人事運用が各府省において行われる一因となっているとの意見があり、人事行政諮問会議の最終提言では、在級期間を廃止することで、年次に縛られず実力本位で活躍できる公務を目指すべきであるとのご指摘をいただいている。人事院としても、採用年次や年齢にとらわれず能力本位で活躍でき、それぞれの職責に応じた処遇を図ることは重要と考えている。その対応策の一つとして、昨年の勧告時報告においても在級期間の廃止も含めた見直しについて言及したところであり、関係者の意見を聴きながら、引き続き検討を進めていきたい。
(3) 諸手当について
諸手当については、民間の状況、公務の実態等を踏まえ、職員団体の御意見も聴きながら、必要となる検討を行っていくこととしたい。
なお、交通用具使用者の通勤手当については、民調結果を踏まえて、支給額の改善等、必要な検討を行ってまいりたい。
また、特地勤務手当等の特地官署等について、国勢調査や全国道路・街路交通情勢調査の最新の結果並びに昨年行った寒冷地手当の支給地域の見直し結果や各府省との間で確認したそれぞれの官署に係る個別の状況を基に、今年度見直すことを予定している。引き続き、職員団体の意見も聴きながら検討を進めてまいりたい。
2.非常勤職員制度等について
(1) 非常勤職員制度の抜本改善等について
非常勤職員の任用、勤務条件等は、その適切な処遇等を確保するため、法律や人事院規則等で規定しており、期間業務職員制度、育児休業制度、休暇制度などについて、これまでも職員団体の意見を聴きながら見直しを行ってきている。今後とも職員団体の意見も伺いながら、民間の状況等を考慮し、適切に対処してまいりたい。
また、人事院では、各府省の実態を踏まえ、昨年、「期間業務職員の再採用時における公募3年要件の見直し」を行い、公募によらない再度の採用の上限回数を連続2回までとする人材局長通知の記載を削除したほか、各府省における円滑な制度運用に資するよう、期間業務職員の採用等に関するQ&Aを発出したところであり、各府省において適切な運用がなされるよう、引き続き、制度の理解促進や助言指導を行うなど取り組んでまいりたい。
(2) 非常勤職員の給与について
非常勤職員の給与については、非常勤職員の給与に関する指針において、基本となる給与は、非常勤職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号俸の俸給月額を基礎として、職務内容及び職務経験等を考慮して決定すること、任期が相当長期にわたる非常勤職員に対しては、期末手当及び勤勉手当に相当する給与を、勤務時間、勤務実績等を考慮の上支給するよう努めることとしている。
また、指針では、給与法等の改正により常勤職員の給与が改定された場合、非常勤職員の給与も、常勤職員に準じて改定するよう努めることとしている。
指針に基づく各府省の取組状況等については、定期的にフォローアップを行っているほか、機会を捉えて各府省から状況を聴取し、必要な指導を行ってきている。今後とも、各府省において指針の内容に沿った適切な処遇が図られるとともに、常勤職員の給与との権衡がより確保されるよう取り組んでまいりたい。
(3) 非常勤職員の休暇等について
非常勤職員の休暇制度等については、業務の必要に応じて、その都度任期や勤務時間が設定されて任用されるという非常勤職員の性格を考慮しつつ、民間の状況等を考慮し、必要な措置を行っているところであり、今後も必要に応じて検討を行ってまいりたい。
なお、近年の措置を挙げれば、結婚休暇の新設及び忌引休暇の対象職員の要件の削除(平成31年1月施行)、夏季休暇の新設(令和2年1月施行)、出生サポート休暇、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の新設並びに産前休暇・産後休暇の有給化(令和4年1月施行)、病気休暇(私傷病)の有給化並びに出生サポート休暇、配偶者出産休暇、育児参加のための休暇、子の看護休暇及び短期介護休暇における取得要件(6月以上の任期又は6月以上の継続勤務)の撤廃(本年4月1日施行)などがある。さらに、本年10月からは、育児時間について、対象となる子の範囲を3歳までの子から小学校就学前までの子に拡大することなどとしている。
3.高齢期雇用について
(1) 定年延長に伴う給与制度の見直しについて
定年の段階的引上げは、令和5年4月から施行されたところ。人事院としては、定年の段階的引上げに係る各種制度が円滑に運用されるよう、引き続き制度の周知や理解促進を図るとともに運用状況の把握に努め、必要に応じて適切に対処してまいりたい。
60歳前後の給与カーブの在り方は、段階的に定年が引き上げられる中での公務における人事管理の在り方の変化や、民間における高齢期雇用や高齢層従業員の給与水準の状況を注視しつつ、職員団体の意見も聴きながら、法律で定められた期限(65歳定年の完成)までに、引き続き検討を行ってまいりたい。
定年引上げに伴う級別定数措置については、今後とも、役降り後の職務や異動先、ポスト数のほか、定年引上げ後の昇格ペースを含む各府省・人事グループの人事運用の状況などを踏まえた上で、必要な級別定数を措置することとしている。
(2) 高齢層職員の勤務条件等の整備について
人事院では、超過勤務命令を行う上限を人事院規則で設定し、令和4年度からは勤務時間調査・指導室が超過勤務時間の適正な管理について指導を行うなど、高齢層職員を含めて超過勤務の縮減に取り組んできている。
また、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員は希望に応じて短時間勤務を行うことが可能であり、短時間勤務職員に超過勤務を命ずる場合には、正規の勤務時間がフルタイム勤務職員より短く定められている趣旨に十分留意しなければならないとされている。交替制勤務についても、短時間勤務職員であれば、フルタイム勤務の場合と比べて正規の勤務時間が短い分、業務負荷は軽減されることになる。
いずれにしても、職員の勤務時間、休暇については、従来より、民間における普及状況に合わせることを基本に、官民均衡の観点から必要があれば適宜見直しを行ってきたところであり、宿直勤務等を行う職員の連続勤務の在り方も含めて高齢層職員に係る民間の動向を注視し必要な検討を行ってまいりたい。
(3) 再任用制度について
再任用職員の給与は、民間の再雇用者の状況も踏まえつつ、俸給と特別給を合わせて適正な年間の給与水準を確保し得るように設定されており、公務における人事運用の実態や民間企業の再雇用者の手当の支給状況を踏まえ、これまでも見直しを行ってきている。昨年の勧告では、人事運用の変化を踏まえ、地域手当の異動保障、住居手当、特地 勤務手当、寒冷地手当等を支給することとしたところであり、引き続き、民間の高齢層従業員の給与の状況や定年前の職員に係る状況を踏まえつつ、職員団体の意見も聴きながら、適切に対応してまいりたい。
また、原則定年年齢を60歳から65歳に段階的に引き上げる改正国家公務員法が令和5年4月1日から施行されており、令和13年度以降の原則定年年齢は65歳となるが、定年の段階的な引上げ期間中の暫定再任用制度においても、できるだけ職員の希望が叶い活躍していただけるよう、人事院としても、引き続き状況の把握に努め、必要な取組を進めてまいりたい。
なお、再任用職員の年次休暇については、再任用は、一旦、退職した職員を新たに職員として採用するものであるため、新たに付与するものとなっている。
4.労働時間、休暇制度等について
(1) 労働時間の短縮等について
人事院は、各府省における勤務時間の客観的把握を開始している部局においては、これに基づき、適正に超過勤務時間を管理することを職員福祉局長通知で求めている。また、勤務時間調査・指導室において、勤務時間の管理等に関する調査を令和4年度から実施しており、対象となる職員ごとに客観的に記録された「在庁時間」と「超過勤務時間」を突合し、かい離があればその理由を確認するなど、客観的な記録を基礎とした超過勤務時間の適正な管理について指導を行っているほか、他律部署・特例業務の範囲について慎重に判断するよう指導している。令和5年度からは同室が地方の官署を直接訪問する形式の調査を実施しているほか、昨年度からは調査対象の職員数を増やすなど、調査・指導を充実させている。
超過勤務命令の方法については、課室長等による超過勤務予定の事前確認や、所要見込み時間と異なる場合の課室長への事後報告を適切に行うことを職員福祉局長通知で求めており、勤務時間調査・指導室が行う調査において、適切な運用に向けた指導・助言を行っている。
また、本年3月に、月100時間や平均月80時間の上限を超える超過勤務をさせる場合の特例業務の範囲をより慎重に判断することなどを求める通知改正を行ったところ、各府省に対する指導を適切に行ってまいりたい。
人事院としては、引き続き、客観的に記録された在庁時間を基礎とした超過勤務時間の適正な管理について指導を行うことを通じて、適正な勤務時間管理につなげてまいりたい。
(2) 勤務間のインターバル確保について
勤務間のインターバル確保について、各省各庁の長の責務を法令上明確にするため、昨年4月より、人事院規則に努力義務規定を導入している。加えて、具体的な取組の検討を支援するため局長通知を発出し、勤務間のインターバルの目安となる時間(11時間)や、確保に向けた取組の例を示しているほか、日々確保することが困難である場合であっても、職員が睡眠時間を含む生活時間を少しでも長く確保できるよう各職場において努めること等を求めている。
人事院としても、これらの取組を各職場へ浸透させることが重要と考えており、職員向けの周知資料を作成・公表しているほか、各府省に対しても、勤務間のインターバル確保に係る調査・研究事業の結果も踏まえつつ、交替制等勤務職員をはじめ、各職場で勤務間のインターバル確保が図られるよう取り組んでまいりたい。
(3) 両立支援制度を含む休暇制度等の改善について
両立支援制度を含む職員の休暇、休業等については、従来より情勢適応の原則の下、民間における普及状況に合わせることを基本に、適宜見直しを行ってきたところであり、引き続き民間の動向等を注視してまいりたい。
両立支援制度については、昨年5月に成立した「民間育児・介護休業法等の一部を改正する法律」の内容も踏まえ、昨年8月に、現行の育児時間(1日につき2時間の範囲内)に加え、1年につき10日の相当時間数の範囲内で勤務しないことができる育児時間のパターンを新たに設けること等を内容とする国家公務員育児休業法の改正についての意見の申し出を行った。昨年12月これを踏まえた改正育児休業法が成立し、本年10月から施行される予定である。あわせて、昨年12月には、子の看護休暇の取得事由の拡大(入園式・卒園式・入学式などの式典参加、感染症による学級閉鎖等を追加)や取得の対象となる子の年齢の拡大(小学校3年生までの子)を内容とする人事院規則の改正を行い、本年4月から施行されている。
また、育児又は介護にかかる両立支援制度を利用しやすい勤務環境整備のため、昨年度中に人事院規則等の改正を行い、育児期の職員及び家族の介護に直面した旨を申し出た職員等への面談等による制度周知や意向聴取等を各省各庁の長に義務付けることとし、介護については本年4月から、育児については本年10月から施行することとした。
(4) 男女平等・共同参画の推進について
性別による差別については、国家公務員法に定める平等取扱いの原則(第27条)により禁止されているほか、人事院規則8―12においてもその旨明らかにしているところ。また、平等取扱の原則に違反して差別をした者については罰則(第109条第8号)が設けられているところである。
人事院としては、公務における女性の活躍推進を人事行政における重要な課題の一つと認識しており、国家公務員法に定める平等取扱いの原則、成績主義の原則の枠組みを前提とした女性の参画のための採用・登用の拡大、両立支援、ハラスメント防止対策など様々な施策を行ってきているところ。引き続き各府省の具体的な取組みが進むよう支援してまいりたい。
(5) 性的マイノリティ職員への対応等について
職員の任免については、人事院規則8-12で、国家公務員法第27条の平等取扱いの原則等に違反して行ってはならないとされている。
また、人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)で、セクシュアル・ハラスメントは禁止されており、同規則運用通知において、性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動がセクシュアル・ハラスメントに含まれることを明確にしている。また、同規則に基づく指針において、「性的指向・性自認を本人の承諾なしに第三者に漏らしたりすること」(いわゆるアウティング)をセクシュアル・ハラスメントになり得る言動として例示している。こうした内容について研修等により各府省への周知・啓発を行うとともに、ハラスメントに係る相談体制も整備している。
そして、これらの施策や取組に基づき、各府省において適切な措置が講じられることにより、性的指向・性自認に関する差別やハラスメントのない職場環境を実現していくことが重要と認識している。
人事院としても、今後も、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(LGBT理解増進法)に基づく基本計画や指針等の策定に向けた政府全体での検討を踏まえながら、適切に取り組んでまいりたい。
なお、人事院の所管する国家公務員の手当制度、休暇制度等各種制度においては、配偶者に加えて「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」も対象としている場合があるが、そこに同性パートナーが含まれ得るかどうかは、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づき、民法上の考え方や民間労働法制における整理も踏まえて検討する必要があると考えている。
5.健康確保等について
(1) 心の健康づくり対策について
心の健康づくり対策については、「職員の心の健康づくりのための指針」を基本として、管理監督者をはじめとする職員に対する研修の充実・強化、「こころの健康相談室」や「こころの健康にかかる職場復帰相談室」の運営等に取り組んでいる。また、心の不調を未然に防止するためのストレスチェックの実施については、各府省への普及啓発を行い、取組を促進している。
さらに、本年5月には、精神保健・産業保健分野の有識者の協力を得て、国家公務員の心の健康の問題による長期病休者の円滑な職場復帰のための「職員向け手引き」及び「担当者向けマニュアル」を作成し、各府省に提供した。
引き続き、これらの手引き・マニュアルの活用について周知するなど、心の健康づくり対策に努めてまいりたい。
(2) ハラスメントの防止について
人事院は、ハラスメント防止等の措置を講じるための人事院規則等に基づき、これまで、研修教材の作成・提供や、各府省のハラスメント相談員を対象としたセミナーの開催など、各府省に対する支援を行ってきている。
また、令和5年度から「幹部・管理職員ハラスメント防止研修」について、組織マネジメントの観点も反映したより実効性のあるものとなるよう見直して実施してきているほか、本年3月にはハラスメント相談員向けの専門家の相談窓口の設置をしたところ。
今後も、各府省のハラスメント防止対策の実施状況を把握するほか、各府省の相談員を対象としたセミナーの開催、研修用教材の改訂等を外部の専門家と連携しつつ行うなど、各府省においてハラスメント防止対策が適切に実施されるよう支援・指導を行ってまいりたい。
なお、公務においては、職員が担当する行政サービスの利用者等からの言動も人事院規則上のパワー・ハラスメントになり得るものであり、人事院では、各省各庁の長に対して、「組織として対応し、その内容に応じて、迅速かつ適切に職員の救済を図ること」を求めている。これらを周知・啓発するため、昨年12月のハラスメント防止週間において、カスタマー・ハラスメントへの対応に特化したポスターを作成し各府省に提供したところ。今後、これらに加え、幹部・管理職員等を対象とした研修等を通じて、各府省には、カスタマー・ハラスメントから職員を守る責務があることや過度な要求に対しては毅然とした対応も求められることについて認識を広げていくとともに、民間労働法制等の内容を踏まえ、カスタマー・ハラスメントに関してどのように人事院規則等で定めるかを含め、対応を検討してまいりたい。
地域間格差などあらゆる格差の解消を
以上の中間回答を受けて、公務労組連絡会側は主に以下の点にかかわって追及しました。
〇 24年度の国家公務員採用試験の一般職の申込状況は、23年度から6.1%も減少し、若年層の離職者も増加している。その理由は賃金だけではないとしても、国家公務員試験の高卒初任給が最低賃金水準にとどまっている現状は早急に改善すべきだ。
○ 人事行政諮問会議の最終提言では、本府省等で働く一部の職員に限定して比較企業規模を「1,000人以上」とすることが提案されているが、全職員を対象に企業規模を1,000人以上とし、地域間格差、正規と非正規の格差など、あらゆる格差を解消せよ。
○ 非常勤職員について、同一労働同一賃金の徹底をはかり、休暇制度などの改善を求める。特に、年次有給休暇の採用時付与を強く求める。また、公募制について改善がはかられたが、制度が恣意的に運用され、杓子定規に公募が実施されることのないよう、人事院として各府省に指導せよ。
○ 長時間過重労働の解消へ、労基法の36協定のような実効性のある残業規制、客観的な労働時間の把握、定員管理政策の抜本的な見直しと必要な定員措置が極めて重要だ。総定員法を柱とした定員政策の抜本的転換を、人事院として政府に提言せよ。
○ 人事行政諮問会議の最終提言の具体化にあたっては、公務労組連絡会との協議をしっかりおこない、現場の理解と協力、納得と合意を前提にすすめよ。最終回答までに、人事院として検討状況について具体的な報告を求める。
最後に桜井議長が「人事院が労働基本権の『代償機関』というならば、労働者側に寄り添った対応が求められている。最終交渉では誠意ある回答を行うよう強く求める」とのべて交渉を終えました。
以 上 [...] Read more...
2025年7月17日物価高のもと賃金改善は使用者の責任だ
= 夏季重点要求をめぐって内閣人事局と中間交渉 =
公務労組連絡会は7月17日、政府・内閣人事局と「2025年夏季重点要求書」に対する中間交渉を行いました。
交渉には、桜井議長を先頭に、檀原(だんばら)副議長、香月事務局長以下6名が参加、内閣人事局は次田亜美総括参事官補佐ほかが対応しました。
切実な増員要求には何ら言及なし
中間交渉にあたって桜井議長は、「物価高のもと消費税減税が参議院選挙の争点となっている。生活改善へ大幅な賃上げが切実に求められている。また、長時間過密労働を解消するため、業務量に見合った人員配置を求める」とのべ、夏季重点要求に対する中間的な回答を求めました。
「1 賃金の改善等」に関し、国家公務員の給与改定に当たっては、国家公務員の適正な処遇の確保や、国民の理解を得る観点からも、また、労働基本権制約の代償措置といった観点からも、第三者機関としての人事院が専門的見地から行った官民比較に基づく人事院勧告を尊重することが政府としての基本姿勢である。今後も、諸情勢を踏まえつつ、対応していく。
「2 非常勤職員制度の抜本改善」に関し、非常勤職員の常勤化・定員化については、国家公務員の場合、
・ 非常勤職員の官職は、常勤の官職とは、業務の性質や職務の内容が異なるものであること
・ また、非常勤職員を常勤職員の官職に任用するためには、国家公務員法に基づき、採用試験などにより、常勤職員としての能力の実証を行う必要があること
から、困難であると考えている。
無期転換制度については、国家公務員の場合、常勤職員として採用するには、国家公務員法に基づき、採用試験などによって、常勤職員としての能力の実証を行う必要があることから、困難であることを御理解いただきたい。なお、非常勤職員についても、公開・平等の採用試験など常勤職員としての能力の実証を行う手続に応募する機会は広く与えられており、こうした手続を経て常勤職員として採用されることはあり得るものと考えている。
非常勤職員の任用については、例えば期間業務職員に関して、人事院において、各府省や職員団体の意見等も踏まえながら、制度官庁と協議をした上、各府省における円滑な運用に資するよう「期間業務職員の採用等に関するQ&A」を昨年11月に作成したと承知している。これを踏まえ、内閣人事局としては、昨年11月に各府省に対し、期間業務職員の再採用に当たって適切に運用を行うよう周知を行ったところであり、引き続き各府省の運用を注視しつつ、必要に応じて適切な対応を検討してまいりたい。
非常勤職員の処遇改善に係る取組として、まず、給与については、人事院において、常勤職員との均衡をより一層確保することを目的として、一昨年4月に非常勤職員の給与に関する指針を改正し、給与法等の改正により常勤職員の給与が改定された場合には、非常勤職員の給与についても、常勤職員に準じて改定するよう努める旨を追加し、この指針に沿った適切な給与支給が行われるよう、各府省を指導していくものと承知している。なお、給与の遡及改定については、昨年12月に人事院と内閣人事局から改めて周知を図ったところ。
休暇・休業については、昨年の国家公務員の育児休業等に関する法律の改正により、育児時間について、新たな選択肢を追加し、対象となる子の範囲を拡大するとともに介護休暇等の取得要件の緩和などの制度改正を行うなど、着実に整備を進めてきているところである。
引き続き、人事院とも連携し、各府省に対して、非常勤職員に関する給与や休暇等の制度の適切な運用を促してまいりたい。
「3、国民本位の行財政・司法の確立」に関し、定員管理については、国民のニーズを踏まえて、新たな行政需要に的確に対応していくためには、既存の業務を不断に見直し、定員の再配置を推進していくことが重要である。
その上で、新たな行政課題や既存業務の増大に対応するため、各府省官房等から現場の実情を聴取しつつ必要な行政分野に必要な増員を行っているところ。
引き続き、既存業務の見直しに積極的に取り組みながら、内閣の重要政策に適切に対応できる体制の構築を図ることとしている。
「4 高齢期雇用・定年延長」に関しては、シニア職員がその知識・経験を存分に発揮し、働き方改革等にもつながるよう、「国家公務員の定年引上げに向けた取組指針」を踏まえた取組を計画的かつ着実に進めてまいりたい。
なお、定年引上げ期間中においては、令和6年度から2年に1度、定年退職者が発生しないことによる新規採用への影響を緩和するための措置を行うこととしており、令和6年度は、特例的な定員を1年間の期限付の定員として1,829人措置することとしたところ。
「5、民主的公務員制度と労働基本権の確立」に関して、自律的労使関係制度については、多岐にわたる課題があることから、皆様と誠実に意見交換しつつ、慎重に検討してまいりたいと考えている。
「6 労働時間短縮など働くルールの確立」に関し、超過勤務の縮減のため、各府省等は、「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」等に基づき、業務の廃止・効率化、デジタル化、マネジメント改革推進のための取組等を進めている。今後とも、勤務時間などの基準を定めている人事院と連携して超過勤務の縮減に取り組んでまいりたい。
障害者雇用については、人事院が策定した合理的配慮に関する指針等を踏まえ、「公務部門における障害者雇用マニュアル」を令和6年1月に改訂するなど、環境の整備に取り組んでいるところ。
また、性的マイノリティをめぐる職場環境の改善等については、平成28年以降、各府省等の人事担当者等を含む全職員を対象とした勉強会等を開催し、国家公務員の性的指向・ジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解の促進に取り組んでいるところ。
今後も全ての職員が働きづらさや不安を感じることなく、安心して働き続けることができる職場にしていくよう取り組んでまいりたい。
「7 両立支援制度の拡充、男女平等・共同参画の推進」に関し、育児休業については、昨年の民間労働法制の改正により民間労働者に認められた措置に相当するものとして、国家公務員の育児休業等に関する法律を改正し、新たな選択肢を追加するなどの制度改正を行ったところである。引き続き、民間労働法制の動きを注視してまいりたい。
「8 健康・安全確保等」に関し、内閣人事局としては、各府省の取組を補完するため、パワー・ハラスメントやカスタマー・ハラスメントを含むハラスメント防止講習を提供しているところ。なお、ハラスメント防止に関する研修は管理職員、課長補佐、係長に加え、幹部職員、課長等への昇任時にも受講を必修としている。
また、「国家公務員健康増進等基本計画」では、各府省における相談窓口の実施状況や利便性等をフォローアップすることとしており、この結果を踏まえ、各府省の取組を支援してまいりたい。
非常勤職員の無期雇用転換と処遇改善を
これに対して公務労組連絡会側は、職場実態をふまえつつ主に以下の点について追及しました。
〇 物価高の一方、実質賃金は下がり続けるなか、公務員賃金が低水準なまま放置されている事態は、使用者・政府として直視すべきだ。すべての世代の公務労働者の大幅賃上げを求める。人事行政諮問会議の「最終提言」では、官民賃金の比較企業規模を「1,000人以上」とすることが示されており、政府としても賃上げを加速させることを求める。
○ 多くの非常勤職員は、これまで定員内職員が行っていた業務を代わって担っている。正規職員との格差是正をすすめ、希望する職員は正規化すべき。非正規職員の賃上げをはじめ処遇改善は、地方経済の活性化だけでなく男女格差の解消をはかる観点から真摯に検討せよ。
○ 長時間過密労働の解消は、公務・公共サービスの拡充において喫緊の課題であることは、労使共有の認識だ。つらつらと施策がのべられたが、何よりも増員が不可欠であり、そのために定員管理政策の抜本的な見直しと必要な定員措置を求める。
〇 昨年のILO(国際労働機関)総会では、第87号条約(結社の自由・団結権保護)に関する日本の適用状況が議論された。労働基本権回復にむけた労使協議をただちに開始せよ。「多岐にわたる課題」があるならば、課題別に整理して具体的な協議を行う場を設けよ。
最後に桜井議長が「基本権回復にむけた具体的な議論をすみやかに開始することを再度強く要求する。本日示された中間回答はきわめて不満だ。最終交渉では納得できる具体的な回答を求める」とのべ、交渉を終えました。
以 上 [...] Read more...
2025年6月13日人事院勧告へ新たなたたかいがスタート
= 人事院・政府に「夏季重点要求書」を提出 =
公務労組連絡会は6月13日、8月の人事院勧告にむけて人事院と内閣人事局に「2025年夏季重点要求書」を提出しました。
要求書の提出は、香月直之事務局長を先頭に、西芳紀・山元幸一の各事務局次長、藤井勇輔書記が参加、人事院は中山博之連絡調査官ほかが、政府・内閣人事局は北浦哲参事官補佐ほかが対応しました。
切実な要求をふまえた真摯な検討を求める
人事院への要求書提出にあたり、香月事務局長は「春闘期では緊急勧告も含めた対応を強く求めてきたが、労働基本権の『代償機関』としての役割を人事院が十分に果たしているとは言いがたい。公務労組連絡会の要求について真摯に検討し、誠実な交渉行うことを求める」と発言しました。
これに対して、中山連絡調査官は、「要求書は確かに受領した。この場での発言も併せて所管部局に正確にお伝えする。今後、勧告までの間のしかるべき時点で会見の場を設け、中間的回答、最終回答を行う」とのべました。
内閣人事局への要求書提出では、この間取り組んできた『政府の責任で物価高騰から生活を守る大幅賃上げ等を求める署名』の追加分を提出、累計で52,470名分となりました。
その上で香月事務局長は「石破首相は『賃上げを起点とした成長型経済の実現』を掲げるが、公務員賃金の大幅改善なしには達成できない。公務員賃金改善へ使用者・政府の政治的決断すべき」と求めました。
これに対して、北浦哲参事官補佐は、「要求の趣旨は承った。要求事項は多岐にわたっているため、検討させていただいた上で、しかるべき時期に回答を行いたい」とのべました。
今後、公務労組連絡会は、7月中旬に中間交渉、下旬から8月上旬頃に最終交渉を配置配置し、職場・地域からのたたかいを背景に要求実現を迫っていきます。
以 上
別添資料(PDFファイル)
(1)人事院あて2025年夏季重点要求書
(2)政府あて2025年夏季重点要求書 [...] Read more...
2025年4月28日人事委員会の使命をふまえ適正な給与水準を確保
= 全人連への要請に中西会長が文書で回答 =
公務労組連絡会は4月9日、自治労連・全教と共同して、地方公務員・教職員の賃金・労働条件の改善を求めて、全国人事委員会連合会(全人連)に要請しました(別添の要請書参照。
この要請に対する中西充会長からの回答が、4月28日に文書で寄せられました。 【中西充全人連会長からの回答】
能登半島地震など災害への対応をはじめ、各地で公務に尽力されている全国の自治体職員の皆様に、改めて敬意を表します。4月9日の要請につきましては、早速、全国の人事委員会にお伝えしたところです。
最近の経済状況を見ますと、去る4月18日に発表された政府の月例経済報告では「景気は、緩やかに回復しているが、米国の通商対策等による不透明感がみられる。」とし、加えて「先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクが高まっている。」としています。
本年の春季労使交渉では、昨年に引き続き多くの大手企業で高い水準の賃金引き上げ、満額回答が示されているほか、初任給を大幅に引き上げる動きも見られます。中小企業では引き続き多くの企業で労使交渉が続いておりますが、そうした賃上げの流れがどこまで波及するか注目されるところです。春季労使交渉の結果は公民較差や特別給の状況に影響を与えることから、今後の行方を注意深く見てまいります。
こうした民間における賃金の状況を的確に把握するため、毎年、各人事委員会は、人事院と共同で民間給与実態調査を行っており、本年の調査期間は4月23日から6月13日までとしております。
この度、要請がありました個々の内容は、各人事委員会において、調査結果や各自治体の実情のほか、社会経済の動向等を踏まえながら、本年の勧告に向けて検討していくことになるものと思います。
私ども人事委員会の重要な使命は、中立かつ公正な第三者機関として、公務員の給与等の勤務条件について、社会情勢に適応した、適正な水準を確保することであると認識しております。
全人連といたしましては、今後も各人事委員会の主体的な取組を支援するとともに、各人事委員会や人事院との意見交換に努めてまいります。
以 上
(添付資料)(PDFファイル)
全人連に提出した要請書 [...] Read more...
2025年4月21日公務・民間が力あわせすべての労働者の賃金改善を
= 公務員賃金署名の20万集約へオンラインミーティング =
全労連・同公務部会・公務労組連絡会は4月21日、25人勧にむけて官民共同でとりくむ『公務労働者の大幅賃上げなどを求める署名』を推進するため、「公務員賃金署名キックオフ」オンラインミーティングを開催しました。
すべての世代の賃上げ、官民給与の比較企業規模の引き上げなど、要求の意思統一をはかりました。
組合未加入者にも協力を呼びかけよう
全労連の黒澤事務局長は主催者あいさつで、「すべての世代の大幅賃上げ、地域間格差の是正・解消の実現、非正規公務員の処遇改善などの運動が極めて重要になっている。そのためにも『公務員賃金署名』を未加入者をふくめて職場でひろげていこう」と呼びかけました。
公務部会賃金・権利専門員会の笹ヶ瀬委員長が、公務員賃金をめぐる情勢と課題を報告しつつ、公務員賃金署名の10の要求項目について丁寧に解説しました。その後、質疑応答を経て、各組織を代表して4名が決意表明しました。
全教の金井書記長は、「給特法改正法案の国会審議で、あべ俊子文科大臣は『所定の勤務時間外に教師が業務を行う時間は、労働基準法の労働時間とは言えない』などと答弁。大きな怒りを感じている。政府法案廃案にむけて教職員だけでなく、広く多くの国民・父母と共同して廃案に追い込みたい」とのべました。
自治労連の橋口書記長は「給与制度のアップデートでは、地域手当について地域間格差がより明確になった。自治労連に結集する単組は、各地で手当引き下げを跳ね返している。全国どこでも安心して生活できるため、抜本的な賃上げで格差是正へたたかう」と決意をのべました。
国公労連の関口中央執行委員は「24人勧では中高年層の賃上げは抑えられ、地域手当等の改悪により実質的に賃下げとなっている。物価上昇はすべての世代に及ぶなか、大幅賃上げにむけ官民共同のたたかいに全力をあげたい」と力強くのべました。
福祉保育労の佐々木副委員長は「25春闘では『みんなの人権を守れる福祉職場に』というスローガンを掲げてたたかい、その中でベースアップを勝ち取った職場がいくつもでてきた。公務労働者の賃金が上がれば、民間賃金にもプラスに影響する。福祉保育労も人勧が上がるよう運動をすすめたい」と決意表明しました。
最後に公務部会の香月事務局長は、「今年の人勧は今後の公務員の働き方、賃金のあり方の方向性を大きく位置付けるものになる可能性がある。人事行政諮問会議の『最終提言』に対して、NOを突き付けていくことが重要だ」とのべ、20万人からの集約を目標とした『公務員賃金改善署名』の推進へ、職場の仲間に声をかけていくことを呼びかけました。
集約された署名は、7月25日に配置している夏季中央行動で提出する予定です。公務・民間の共同で大いにひろげ、すべての労働者の賃金・労働条件改善をめざすことを参加者全体で意思統一し、オンラインミーティングを終了しました。
以 上
[...] Read more...
2025年3月28日「民間準拠」「人勧尊重」の不満な回答
= 春闘統一要求で政府・人事院と最終交渉 =
2月17日に提出した「2025年春闘統一要求書」をめぐって、公務労組連絡会は3月24日に人事院と、また、26日には政府・内閣人事局との最終交渉に臨みました。
春闘要求に対する最終回答をふまえて公務労組連絡会は、「従前の回答から一歩もでない内容」とする幹事会声明(別掲)を発表、引き続き切実な諸要求の前進にむけて奮闘する決意を内外に明らかにしました。
(人事院)今年の勧告にむけて課題は山積
人事院との交渉には、公務労組連絡会の宮下副議長を先頭に、香月事務局長以下幹事会6名が参加、人事院は、給与局第一課の橋本課長補佐、職員福祉局職員福祉課の上村課長補佐らが対応しました。
宮下副議長の求めに応じ、人事院側は以下のような最終回答を示しました。
【人事院最終回答】
1.賃金の改善について
まず、賃金の改善についてです。人事院は、労働基本権制約の代償措置としての勧告制度の意義や役割を踏まえ、情勢適応の原則に基づき、必要な勧告を行うことを基本に臨むこととしています。
俸給や一時金は、国家公務員の給与と民間企業の給与の実態を精緻に調査した上で、その精確な比較を行い、適切に対処します。
諸手当は、民間の状況、官民較差の状況等を踏まえ、必要となる検討を行っていきます。
2.労働時間の短縮、休暇等について
次に、労働時間の短縮、休暇、休業についてです。超過勤務の縮減については、勤務時間調査・指導室において、超過勤務時間の適正な管理について指導を行うとともに、他律部署と特例業務の範囲が必要最小限のものとなるよう指導を行ってきています。令和6年度には調査・指導を更に充実させており、引き続き適切に各府省に対する指導を行っていきます。
両立支援、職員の休暇、休業等については、これまでも民間の普及状況等を見ながら改善を行ってきました。引き続き、職員団体の意見も伺いながら必要な検討を行っていきます。
勤務間のインターバル確保については、制度の内容の各職場への浸透が重要です。調査・研究事業の結果も踏まえながら、引き続き周知・取組の強化を図ります。
3.非常勤職員の処遇改善について
次に、非常勤職員の処遇改善についてです。非常勤職員の任用、勤務条件等については、その適切な処遇等を確保するため、法律や人事院規則等で規定しており、これまでも民間の状況等も考慮しつつ改善を行ってきました。引き続き、職員団体の意見も伺いながら必要な検討を行っていきます。
非常勤職員の給与については、指針に基づく各府省の取組が進んでいます。指針に基づく各府省の取組状況については、定期的にフォローアップし、必要な指導を行うなど、引き続き、常勤職員の給与とのバランスをより確保しうるよう取り組んでいきます。
4.高齢者雇用について
次に、高齢期雇用施策についてです。定年の引上げについては、定年の段階的引上げに係る各種制度が各府省において円滑に運用されるよう、引き続き、制度の周知や理解促進を図るとともに、運用状況の把握に努め、適切に対応します。
定年の引上げに伴う、給与カーブの在り方については、公務における人事管理の変化や、民間における高齢層従業員の給与水準の状況等を注視しつつ、職員団体の意見も伺いながら、職員の役割・貢献に応じた処遇の観点から、他の制度と一体で引き続き検討を行っていきます。
5.女性参画の推進及び多様性の確保について
次に、女性参画の推進及び多様性の確保についてです。女性参画の推進については、これまで柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の整備、超過勤務の縮減、仕事と生活の両立支援策の拡充やハラスメント防止対策など、男女ともに働きやすい勤務環境の整備を積極的に進めてきました。引き続き、各府省の具体的な取組が進むよう支援していきます。
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性の確保については、性的指向や性自認に関する偏見に基づく行動がセクシュアル・ハラスメントに含まれることを制度上明確にし、典型的な言動を示すとともに、研修等による周知・啓発や相談体制の整備などの施策を講じています。今後も、LGBT理解増進法に基づく基本計画や指針等の策定に向けた政府全体での検討を踏まえながら、適切に取り組みます。
6.健康・安全確保等について
次に、健康・安全確保等についてです。ハラスメントの防止については、今後も、各府省のハラスメント防止対策の実施状況を把握するほか、セミナーの開催や研修用教材の改訂など、各府省に対する支援・指導を行っていきます。
カスタマー・ハラスメント対策については、研修等を通じて、各府省に対し、カスタマー・ハラスメントから職員を守る責務があることについて認識を広げていくとともに、更なる対応について研究するなどして、各府省を支援していきます。
官民比較企業規模の引き上げを強く求める
以上の回答を受け、公務労組連絡会側は主に次の点を柱にして追及しました。
○ 賃金改善の勢い、流れを公務にもしっかり反映するためにも、官民比較企業規模の1000人以上への引き上げを求める。また、人事行政諮問会議の最終提言は、賃金に新たな格差や分断を持ち込むことは断じて認められない。公務の現場からすると、机上の空論でしかない。
○ 「給与制度のアップデート」は、十分な労使協議がおこなわれなかったとことは極めて不満だ。今後の見直しの検討作業において労働組合の意見が反映されるよう求める。
○ 長時間労働の是正は、働き続けられるようにするためだけでなく、家庭責任を有する労働者が働き続けるためにも重要だ。若手職員の離職の増加の要因ともなっており、長時間労働の是正を求める。
○ 非常勤職員の雇用安定と処遇改善は、人材確保や行政サービスの安定につながる。公募制の廃止は強い要求であることを重ねて申し上げておく。加えて、年次有給休暇の採用時からの付与を強く求める。
○ 人事院勧告が、労働基本権制約の「代償措置」ならば、公務労働者の立場に立った検討がなされるべきなのに、そうした実感がない。私たちの要求に対して、最終回答のどこに反映されているのか。
締めくくりに宮下副議長は、「人事院は切実な要求を真摯に受け止めよ。勧告に向けた要求については、改めてとりまとめたうえで提出するので、誠意ある対応を求める」とのべ、春闘期の交渉を閉じました。 (内閣人事局)使用者責任なく人事院に丸投げ
内閣人事局との交渉には、公務労組連絡会は桜井議長を先頭にして臨み、内閣人事局は駒崎総括参事官補佐ほかが対応しました。
交渉の冒頭、桜井議長は組合員の切実な要求を真摯に受け止めるよう求めたうえ、駒崎総括参事官補佐は、「本日は大臣多忙のため、私からこれまでの検討結果を踏まえた最終回答をさせていただく」と断ったうえで、以下の最終回答を示しました。
【内閣人事局・最終回答】
● 優秀な人材を確保し、国家公務員の職員の皆様が働きがいをもって生き生きと働けるよう、私の立場からも国家公務員の処遇改善に向けて取り組んでいきたいと思います。引き続き、現場の実情を含め、皆様からもご提案をいただきながら、前に進めますので、皆様方のご協力をお願いします。
● 令和7年度の給与については、人事院勧告を踏まえ、国政全般の観点から検討を行い、方針を決定したいと考えています。その際には、皆様とも十分に意見交換を行います。
● 非常勤職員については、引き続き、適正な処遇が確保されるよう、関係機関とも連携して、必要な取組を進めてまいります。
● 自律的労使関係制度については、多岐にわたる課題があることから、皆様と誠実に意見交換しつつ、慎重に検討してまいります。
● 最後になりますが、今後とも皆様とは誠意を持った話合いによる一層の意思疎通に努めてまいります。
なお、その他の要求事項への回答については、中間回答で申し上げたとおりです。
ILO勧告ふまえ労使協議の場を設けよ
これに対して、公務労組連絡会側は主に次の点を中心に追及しました。
○ 賃上げ要求に対して、人事院勧告を踏まえるとの回答にとどまったが、使用者としてそれでいいのか。勧告制度があったとしても、賃金改善は政府の責任だ。人材確保のために初任給改善は当然としても、中高齢層の賃金改善が放置されている。生活を守る責任はないのか。
○ 55歳超職員の昇給停止をやめるよう繰り返し求めてきたが、最終回答では示されなかった。業務内容でも、責任の度合いでも、ベテラン職員の役割は前にも増して重くなっている。なのに昇給がストップされるのは不合理だ。若い職員も将来の希望を失う。55歳職員の昇給停止に関わって再回答を求める。
○ 業務量に見合った必要な正規職員の配置をすることを前提にしつつ、非正規公務員の雇用安定にむけて、民間と同様に無期転換制度の導入をはじめ、任期の定めのない短時間公務員制度の創設などを求める。
○ 労働本権回復の要求は、昨年と一字一句文言が変わらない回答にとどまった。ILO勧告をふまえ労働基本権をめぐる労組協議の場をすみやかに設けるべきだ。
これに対して内閣人事局側は、「給与改定にあたっては、人事院勧告制度を尊重することが基本姿勢だ」とするこれまでの回答を繰り返すのみで、また、高年齢の昇給抑制も、「人事院における所要の検討の内容を踏まえ適切に対応する」などとのべ、使用者責任は見られませんでした。
さらに、強く求めてきた労働基本権回復にむけた労使協議については、「自律的労使関係制度について多岐にわたる課題がある」とし、「慎重に検討を進める必要がある」などと、問題解決へ前に進む姿勢はありませでした。
最後に桜井議長は、引き続く公務労組連絡会との真摯な対応を求めて、春闘期における政府交渉を閉じました。
以 上
(別添)25年春闘最終回答への幹事会声明 [...] Read more...
2025年3月14日物価高騰に対応した緊急勧告を出せ
= 25春闘要求で人事院と中間交渉 =
公務労組連絡会は3月14日、「2025年春闘統一要求書」をめぐる中間交渉に取り組みました。
交渉には、公務労組連絡会の桜井議長を先頭に、宮下副議長、香月事務局長以下幹事会6名が参加、人事院は職員福祉課の上村課長補佐、給与局給与第一課の橋本課長補佐ほかが対応しました。
平等取扱いの原則は非常勤職員にも適用
はじめに桜井議長は、「民間大手の労使交渉はヤマ場を超えたが、中小企業や非正規労働者の賃金改善にまでは及んでいない。私たちはこの春闘で、政府に対して政策的賃上げを要求しているが、人事院には物価高騰に対応した緊急な勧告を強く求めます」とのべ、現時点における人事院での中間的な回答を促しました。
これに対し、人事院側は以下の中間的な回答を示しました。
1.賃金の改善について
国家公務員の給与改定については、今後とも、情勢適応の原則に基づき、民間準拠により適正な給与水準を確保するという基本姿勢に立ったうえで、職員団体の意見も聴きながら、適切に対処してまいりたい。
官民給与の比較を行う際の企業規模については様々な議論があるが、国家公務員の給与については、社会的な御理解、関係各方面の御理解が得られるものであることが重要と考えている。比較対象とする企業規模の在り方については、人材確保の要請も考慮した適切な報酬水準を設定していく必要性を踏まえつつ、各方面の意見を伺いながら、検討を行ってまいりたい。
諸手当については、給与制度のアップデートの中で見直しを行ったところであるが、引き続き、民間の状況、公務の実態等を踏まえ、職員団体の意見も聴きながら、必要となる検討を行っていくこととしたい。
2.非常勤職員制度の抜本改善について
○ 非常勤職員制度の抜本改善について
非常勤職員の任用、勤務条件等については、その適切な処遇等を確保するため、法律や人事院規則等で規定しており、これまでも職員団体の意見も聴きながら見直しを行ってきているところである。
○ 雇用の安定と身分保障の確立について
国家公務員法において、公正な人事管理を行うために、平等取扱いの原則(第27条)や、任免の根本基準(成績主義の原則・第33条)等が定められており、これは非常勤職員の任用に対しても適用される。
国家公務員法の平等取扱いの原則及び任免の根本基準に照らし、非常勤職員を含む職員の採用・再採用に当たっては、国民に広く平等に官職を公開し、最も能力・適性の面から優れた者を公正に任用することが求められることから、原則として公募を経ることが必要である。その場合であっても、非常勤職員である者が、新たな非常勤職員の官職の公募に応募し、能力実証の結果任用されることも可能であり、勤務年数等を理由とした「雇い止め」を行う仕組みではない。
人事院としては、昨年、各府省の実態を踏まえ、公募によらない再度の採用の上限回数を連続2回までとする人事院人材局長通知の記載を削除したほか、各府省における円滑な制度運用に資するよう、期間業務職員の採用等に関するQ&Aを発出したところ。今後とも、期間業務職員制度が各府省において適切に運用されるよう、制度の周知や理解増進を図ってまいりたい。
○ 均等・均衡待遇の確立について
非常勤職員の給与については、平成20年8月に非常勤職員の給与に関する指針を発出し、各府省において適正な給与の支給が行われるよう、必要な指導を行ってきている。この指針については、非常勤職員の処遇を確保する観点から累次改定を行ってきており、令和5年4月からは、給与法等の改正により常勤職員の給与が改定された場合には、非常勤職員の給与についても、常勤職員に準じて遡及改定するよう努める旨を追加したところである。各府省においては、この指針に基づく取組が進んでいるところであり、引き続き、常勤職員の給与との権衡をより確保し得るよう取り組んでまいりたい。
非常勤職員の休暇制度等については、業務の必要に応じてその都度任期や勤務時間が設定されて任用されるという非常勤職員の性格を考慮しつつ、民間の状況等を考慮し、必要な措置を行っている。近年の措置を挙げれば、夏季休暇の新設、出生サポート休暇、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の新設並びに産前休暇・産後休暇の有給化などがある。また、令和6年12月には、病気休暇(私傷病)について有給の休暇へ見直すとともに、子の看護休暇等及び短期介護休暇の取得要件の緩和などの見直し(令和7年4月施行)を行ったところである。
今後も、引き続き民間の状況等について注視し、必要に応じて検討を行ってまいりたい。
3.高齢期雇用について
○ 高齢期雇用・定年延長について
定年の段階的引上げに係る各種制度が各府省において円滑に運用されるよう、引き続き、制度の周知や理解促進を図るとともに、運用状況の把握に努め、必要に応じて適切に対応してまいりたい。
令和3年に成立した定年引上げに係る国家公務員法等の改正の基となった平成30年の意見の申出においては、定年引上げ後の60歳を超える職員の給与水準について、民間企業における高齢期雇用の実情を考慮し、当分の間の措置として、60歳前の7割の水準となるよう、給与制度を設計することとしたものである。
他方、改正法に設けられた検討条項では、給与水準が60歳前後で連続的なものとなるよう、定年の段階的引上げが完成するまでに給与制度について所要の措置を講ずることとされている。
人事院としては、60歳前も含めた給与カーブの在り方について、段階的に定年が引き上げられる中での公務における人事管理の在り方の変化や、民間における高齢期雇用や高齢層従業員の給与水準の状況を注視しつつ、職員団体の意見も聴きながら、職員の役割・貢献に応じた処遇の観点から、人事管理に係る他の制度と一体で引き続き検討を行ってまいりたい。
定年引上げに伴う級別定数措置については、今後とも、役降り後の職務や異動先、ポスト数のほか、定年引上げ後の昇格ペースを含む人事運用などに関する各府省・人事グループの検討を踏まえた上で、必要な級別定数を措置することとしている。
○ 再任用職員制度について
再任用職員の給与については、民間の再雇用者の状況も踏まえつつ、俸給と特別給を合わせて適正な年間の給与水準を確保し得るように設定されており、公務における人事運用の実態や民間企業の再雇用者の手当の支給状況を踏まえ、これまでも見直しを行ってきているところである。
近年、高齢層職員の能力及び経験の活用が進められてきている中で、再任用職員が公務上の必要性により転居を伴う異動を行う場合があるなど、人事運用の変化が生じてきている。こうした状況を踏まえ、人事院としては、給与制度のアップデートの一環として、定年前再任用短時間勤務職員や暫定再任用職員について多様な人事配置を可能とし、その活躍を支援するため、再任用職員に支給される手当の範囲を拡大した。再任用の給与については、引き続き、民間の高齢層従業員の給与の状況や定年前の職員に係る状況を踏まえつつ、適切に対応してまいりたい。
なお、再任用職員の年次休暇については、再任用は、一旦、退職した職員を新たに職員として採用するものであるため、新たに年次休暇を付与するものとなっている。
4.労働時間短縮、休暇制度等について
○ 超過勤務の縮減等について
超過勤務の縮減等については、勤務時間調査・指導室において、各府省を直接訪問して勤務時間の管理等に関する調査を令和4年度から実施しており、他律部署・特例業務の範囲が必要最小限のものとなるよう指導するなどしている。令和6年度は、調査・指導を更に充実させる観点から、対象となる職員数を増やして実施しており、引き続き、適切に各府省に対する指導を行ってまいりたい。
勤務間のインターバル確保については、人事院規則や局長通知の内容を各職場へ浸透させることが重要と考えており、職員向けの分かりやすい周知資料を作成・公表しているほか、各府省に対しても、現在実施している勤務間のインターバル確保に係る調査・研究事業などの機会を通じ、随時周知依頼を行っているところである。
○ 休暇・休業制度について
職員の休暇、休業については、従来より情勢適応の原則の下、民間における普及状況に合わせることを基本に、適宜見直しを行ってきたところである。今後も社会情勢等を踏まえつつ、制度の改善や環境整備に努めてまいりたい。
○ 性的マイノリティをめぐる職場環境の改善等について
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性については、人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)において職員はセクシュアル・ハラスメントをしてはならないと規定するとともに、同規則運用通知において偏見に基づく言動がセクシュアル・ハラスメントに含まれることを制度上明確にしており、令和2年4月には、「性的指向・性自認を本人の承諾なしに第三者に漏らしたりすること」(いわゆるアウティング)をセクシュアル・ハラスメントになり得る言動として例示するなどの施策を講じた。また、これらの施策について研修等により各府省への周知・啓発を行うとともに、ハラスメントに係る相談体制も整備している。
今後も、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(LGBT理解増進法)に基づく基本計画や指針等の策定に向けた政府全体での検討を踏まえながら、適切に取り組んでまいりたい。
勤務条件等に関わる各種制度において、配偶者に加えて「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」も対象としている場合に、同性パートナーが含まれ得るかどうかについては、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づき、民法上の考え方や民間労働法制における整理も踏まえて検討する必要があると考えている。
5.民主的公務員制度等について
○ 人事評価について
人事評価については、令和3年10月から、人材育成・マネジメントを強化するための組織改革・育成ツールとして活用することとされている。具体的には、人事評価において、職員の秀でている点(強み)・改善点(弱み)を明確に把握できるようにするとともに、面談を職員の中長期のキャリア形成支援の場として活用するため、その充実等が行われたものと承知している。
また、国家公務員法においては、人事評価が「任用、給与、分限その他の人事管理の基礎」となるものとして位置付けられており、人事院規則等において、能力・実績に基づく人事管理を推進する観点から、評価結果を任免や給与の決定に活用する基準を定めているところである。
6.両立支援制度の拡充等について
○ 両立支援制度について
育児や介護と仕事の両立支援制度については、昨年5月に成立した育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)の内容も踏まえ、国家公務員育児休業法の改正についての意見の申出を国会・内閣に提出し、昨年12月にこれを踏まえた改正育児休業法が成立したところ。これに加え、人事院規則の改正等を行うことにより各種の拡充を行うこととしている。
人事院は、これまでも、両立支援制度を含む職員の休暇、休業等については、情勢適応の原則の下、民間における状況等を踏まえて、必要な見直しを行ってきており、社会情勢等も踏まえながら、引き続き必要な制度改善の検討を行ってまいりたい。
○ 男女平等・共同参画について
女性参画の推進については、人事院としても、これまで柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の整備、超過勤務の縮減、仕事と生活の両立支援策の拡充やハラスメント防止対策など、男女ともに働きやすい勤務環境の整備を積極的に進めており、女性の採用・登用の拡大に向けた様々な施策を行ってきているところである。引き続き、各府省の具体的な取組が進むよう支援してまいりたい。
7.健康・安全確保等について
○ ハラスメント防止対策について
ハラスメント防止対策については、ハラスメント防止等の措置を講じるための人事院規則等に基づき、これまで、研修教材の作成・提供や、各府省のハラスメント相談員を対象としたセミナーの開催など、各府省に対する支援を行ってきている。
また、昨年度から「幹部・管理職員ハラスメント防止研修」について、組織マネジメントの観点も反映したより実効性のあるものとなるよう見直して実施する等の取組を行っている。
今後も、各府省のハラスメント防止対策の実施状況を把握するほか、各府省のハラスメント相談員を対象としたセミナーの開催、研修用教材の改訂等を外部の専門家と連携しつつ行うなど、各府省においてハラスメント防止対策が適切に実施されるよう、必要な支援・指導を行ってまいりたい。
「民間準拠」ならば比較企業規模を見直せ
この回答に対して、公務労組連絡会側は、民調での比較企業規模を1000人以上に引上げることや、中高年層をふくめてすべての世代の賃金を上げること、非正規公務員の均等待遇による安定した雇用を確保することなどを求めました。
また、「給与制度のアップデート」にかかわって、当事者のいない人事行政諮問会議で議論されていることに強い不満を表明しつつ、誠実な労使協議の実現を求め、とりわけ、一方的な不利益変更は認められないことを強調しました。
最後に桜井議長は「昨年の域を超えておらず、不満な中間回答」としたうえ、「物価高騰のもとで、生活を守るための大幅賃上げを求める声はますます強まっている。さらなる検討をおこない、誠意ある最終回答を示すよう求める」とのべて、中間交渉を閉じました。
以 上 [...] Read more...
2025年3月14日生活守る賃上げへ使用者責任を果たせ
= 春闘要求実現求め内閣人事局交渉 =
公務労組連絡会は3月14日、「2025年春闘統一要求書」および「労働基本権回復など公務員制度等に関する要求書」をめぐって、政府・内閣人事局と中間交渉を行いました。
交渉には、公務労組連絡会の桜井議長を先頭に、宮下副議長、香月事務局長以下幹事会6名が参加、内閣人事局は駒崎総括補佐ほかが対応しました。
交渉にあたって、「政府の責任で物価高騰から生活を守る大幅賃上げ等を求める署名」の第一次分集約として、7,911名分を提出しました(写真)。
賃金も時短も人事院だのみの不満な回答
桜井議長は、「石破首相は『賃上げこそが成長戦略の要』とのべているが、ならば使用者として、公務員賃金こそただちに上げるべきではないのか。政府が率先して、政策的な賃上げを行うことを求める。また、国民の安全・安心を守るうえでも、大幅な増員を強く求める」とのべ、現時点における内閣人事局からの中間的な回答を求めました。
【内閣人事局中間回答】
1.賃金・昇格等の改善
国家公務員の給与改定に当たっては、国家公務員の適正な処遇の確保や、国民の理解を得る観点からも、また、労働基本権制約の代償措置といった観点からも、第三者機関としての人事院が専門的見地から行った官民比較に基づく人事院勧告を尊重することが政府としての基本姿勢である。
今後も、諸情勢を踏まえつつ、対応していく。
2.非常勤職員の雇用の安定・処遇改善
非常勤職員の常勤化・定員化については、国家公務員の場合、
・非常勤職員の官職は、常勤の官職とは、業務の性質や職務の内容が異なるものであること
・また、非常勤職員を常勤職員の官職に任用するためには、国家公務員法に基づき、採用試験などにより、常勤職員としての能力の実証を行う必要があること
から、困難であると考えている。
無期転換制度については、国家公務員の場合、常勤職員として採用するには、国家公務員法に基づき、採用試験などによって、常勤職員としての能力の実証を行う必要があることから、困難であることを御理解いただきたい。
なお、非常勤職員についても、公開・平等の採用試験など常勤職員としての能力の実証を行う手続に応募する機会は広く与えられており、こうした手続を経て常勤職員として採用されることはあり得るものと考えている。
また、非常勤職員の任用については、人事院において、各府省や職員団体の意見等も踏まえながら、制度官庁と協議をした上、各府省における円滑な運用に資するよう「期間業務職員の採用等に関するQ&A」を昨年11月に作成したと承知している。
内閣人事局としては、まずは各府省の運用を注視しつつ、必要に応じて対応を検討してまいりたい。
非常勤職員の処遇改善に係る取組として、まず、給与については、人事院において、常勤職員との均衡をより一層確保することを目的として、一昨年4月に非常勤職員の給与に関する指針を改正し、給与法等の改正により常勤職員の給与が改定された場合には、非常勤職員の給与についても、常勤職員に準じて改定するよう努める旨を追加し、この指針に沿った適切な給与支給が行われるよう、各府省を指導していくものと承知している。
なお、給与の遡及改定については、昨年12月に人事院と内閣人事局から改めて周知を図ったところ。
また、休暇・休業については、昨年の国家公務員の育児休業等に関する法律の改正により、育児時間について、新たな選択肢を追加し、対象となる子の範囲を拡大するとともに介護休暇等の取得要件の緩和などの制度改正を行うなど、着実に整備を進めてきているところである。
引き続き、人事院とも連携し、各府省に対して、非常勤職員に関する給与や休暇等の制度の適切な運用を促してまいりたい。
3.国民本位の行財政・司法の確立と要員確保等
定員管理については、国民のニーズを踏まえて、新たな行政需要に的確に対応していくためには、既存の業務を不断に見直し、定員の再配置を推進していくことが重要である。
その上で、新たな行政課題や既存業務の増大に対応するため、各府省官房等から現場の実情を聴取しつつ必要な行政分野に必要な増員を行っているところ。
引き続き、既存業務の見直しに積極的に取り組みながら、内閣の重要政策に適切に対応できる体制の構築を図ることとしている。
4.高齢期雇用・定年延長
シニア職員がその知識・経験を存分に発揮し、働き方改革等にもつながるよう、「国家公務員の定年引上げに向けた取組指針」を踏まえた取組を計画的かつ着実に進めてまいりたい。
また、定年引上げ期間中においては、令和6年度から2年に1度、定年退職者が発生しないことによる新規採用への影響を緩和するための措置を行うこととした。
5.民主的公務員制度と労働基本権の確立
自律的労使関係制度については、多岐にわたる課題があることから、皆様と誠実に意見交換しつつ、慎重に検討してまいりたい。
6.労働時間短縮、休暇制度など働くルールの確立
超過勤務の縮減のため、各府省等は、「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」等に基づき、業務の廃止・効率化、デジタル化、マネジメント改革推進のための取組等を進めている。今後とも、勤務時間などの基準を定めている人事院と連携して超過勤務の縮減に取り組んでまいりたい。
また、性的マイノリティをめぐる職場環境の改善等については、平成28年以降、各府省等の人事担当者等を含む全職員を対象とした勉強会等を開催し、国家公務員の性的指向・ジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解の促進に取り組んでいるところ。
今後も全ての職員が働きづらさや不安を感じることなく、安心して働き続けることができる職場にしていくよう取り組んでまいりたい。
7.両立支援制度の拡充、男女平等・共同参画の推進
育児休業については、昨年の民間労働法制の改正により民間労働者に認められた措置に相当するものとして、国家公務員の育児休業等に関する法律を改正し、新たな選択肢を追加するなどの制度改正を行ったところである。引き続き、民間労働法制の動きを注視してまいりたい。
8.健康・安全確保、母性保護等
内閣人事局としては、各府省の取組を補完するため、パワー・ハラスメントやカスタマー・ハラスメントを含むハラスメント防止講習を提供しているところ。なお、ハラスメント防止に関する研修は管理職員、課長補佐、係長に加え、幹部職員、課長等への昇任時にも受講を必修としている。
また、「国家公務員健康増進等基本計画」では、各府省における相談窓口の実施状況や利便性等をフォローアップすることとしており、この結果を踏まえ、各府省の取組を支援してまいりたい。
誠意なく「人事院勧告を尊重」を繰り返す
以上の中間回答に対して、公務労組連絡会側は、全世代が生活改善を実感できる賃上げ、非正規公務員の無期雇用化・正規化、増員による長時間過密労働の解消、業務量に見合った人員配置などを中心に内閣人事局を追及しました。
これに対して駒崎総括参事官は、「給与改定にあたっては、国家公務員の給与を情勢に適応させるとの原則の下、人事院勧告制度を尊重することが基本姿勢だ」との回答を繰り返し、非常勤職員の処遇改善については、「人事院における検討を踏まえ、適切に対応したい」とし、また労働時間短縮にかかわっても、「休暇・休業制度及び育児時間・育児短時間勤務制度などの勤務条件に関する内容については、まずは人事院において検討されるものだ」などとのべ、使用者として責任ある態度は見られませんでした。
最後に桜井議長は、「検討途上とはいえ、不満な回答だ。人事院勧告まかせにするのではなく、すべての公務労働者の生活を守るため、使用者としてただちに大幅賃上げを実施せよ。人員増を求める声は切実なものになっている」とのべ、要求についてさらに検討し、25年春闘統一要求に対する最終的な回答を示すよう求めて中間交渉を閉じました。
以 上 [...] Read more...
2025年3月6日25春闘ヤマ場にむけて奮闘を誓い合う
= 3・6中央行動に3,000人の仲間が総結集 =
国民春闘共闘・全労連は3月6日、 全国食健連、建設アクションなどと共同し、25春闘のヤマ場にむけて「国民春闘勝利! 3・6中央総決起行動」を実施しました。
全国から3,000人が集まった総決起集は、日比谷公園野外大音楽堂をあふれさせ、大幅賃上げにむけてたたかう決意を固め合う場となりました。
全労連公務部会・公務労組連絡会は、中央行動に結集するとともに、独自に人事院前での要求行動を実施。「賃金をあげろ!要員を増やせ!格差を改善せよ」など、切実な要求の実現にむけて奮闘しました。
(人事院前)物価高と人不足で職場要求は切実
総決起集会に先だってとりくまれた人事院前の要求行動には、「大幅賃上げ実現!あらゆる格差の解消!非正規公務員の雇止めは許さない」の要求のもとに、公務各単産の仲間が集まりました。
主催者あいさつした桜井公務労組連絡会議長は、「32年ぶりの2%を超える昨年の人事院勧告は、全国の運動の到達点だが、一方で中高年層の賃金はまったく改善されていない。正規・非正規、すべての年代層の労働者の団結で、要求実現へ奮闘しよう」と呼びかけました。
公務労組連絡会の吹上事務局次長の情勢報告を受けて、5人が決意表明し、国公労連・国土交通労組羽田航空支部の参加者は、「物価高騰に見合う賃上げになっていないと、野菜など買い物をすると実感する。子育て世代、中高年職員にとっては深刻だ。すべての世代の賃上げを求めてたたかっていく」とのべました。
全教からは、「子どもたちに必要な教育を保障するため、教職員を増やし、時間外勤務手当を支払う仕組みをつくることが求められている」(愛知県高教組)、「教職員の人員不足は深刻だ。多くの学校で人員定数を満たせておらず、例え定数を満たしても、教職員が足りないという事態になっている。職場への人的な支援が必要である」(香川県高教)との訴えがつづきました。
国公労連・中部ブロック国公議長は、「国家公務員として長年勤めてきた高年層の賃金が物価高に追いついていない。すべての世代が安心して働ける職場をつくることが、日本経済全体の発展につながる」とのべ、山口自治労連からは、「人事院はアップデートで中高年層の給与を上げるとしているが、山口県では『アップデート』の対象者は、職員全体の1%にすぎない。引き続き運動を強めていく」と決意表明しました。
最後に公務部会代表委員の日巻郵政ユニオン委員長のリードで、力強くシュプレヒコールを人事院にぶつけ、要求行動を終えました。
以 上 [...] Read more...
2025年2月28日全国で働く地方公務員の賃金・労働条件改善を
= 公務労組連絡会の要請に中西会長が回答 =
公務労組連絡会は2月6日、自治体職員・教職員の賃金・労働条件の改善を求めて、全国人事委員会連合会(全人連)への要請にとりくみました。
要請には、香月事務局長、橋口自治労連書記長、檀原全教書記長らが参加、全人連は田中事務局長が対応しました。
この要請に対する全人連会長の回答が、2月28日に文書で寄せられました。
25春闘の賃金引き上げの流れに注視
【中西充全人連会長からの回答】
2月6日の要請につきましては、早速、全国の人事委員会にお伝えしたところです。
最近の経済状況を見ますと、去る2月19日に発表された政府の月例経済報告では、「景気は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している。」とし、先行きについては、「緩やかな回復が続くことが期待される。」ただし、「海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、通商政策などアメリカの政策動向、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。」としています。
本年の春季労使交渉では、物価上昇や人材確保への対応を契機に、労使間において、賃金引き上げの動きがどこまで広がるかについて議論されており、今後の行方を注意深く見ていく必要があると考えております。
また、企業においては、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進、DXによる業務効率化など働き方改革を推進しているところであり、今後の動向を引き続き注視してまいります。
現在、人事院及び各人事委員会では、民間給与の実態を的確に把握できるよう、本年の民間給与実態調査の実施に向け、その準備を進めているところです。
今後、各人事委員会においては、社会経済の動向なども踏まえながら、このたびの要請内容も含め、本年の勧告に向けた検討を進めていくことになるものと思います。
改めて申すまでもありませんが、公務員の給与等の勤務条件について、社会情勢に適応した適正な水準を確保することは、人事委員会の重要な使命であると認識しております。
全人連といたしましては、今後も各人事委員会の主体的な取組を支援するとともに、各人事委員会や人事院との意見交換に努めてまいります。
以 上
(添付資料)
全人連に提出した要請書(PDFファイル) [...] Read more...
2025年2月20日公務・民間が力合わせ大幅賃上げを勝ち取ろう
= 春闘要求実現めざして有楽町で共同宣伝行動 =
全労連公務部会は2月20日夕刻、民間部会と共同してJR有楽町駅頭で宣伝行動にとりくみました。
公務・民間あわせて70人の参加者が、25春闘ビラの入ったティッシュを配布。3月の春闘ヤマ場の回答に向けて大幅賃上げ、労働条件改善、公務・公共サービスの実現を、勤務帰りの会社員や繁華街を歩く多くの人々に訴えました。
劣悪な労働条件は住民サービスの低下と直結
全教の波岡知朗副委員長は、教職員の長時間過密労働を背景にして7千人もの休職者が出ている現状をのべ、「この実態を解消するには人員増しかない。国会では給特法が審議されるなか、世論と運動を強めて教員の増員を勝ち取りたい」と訴えました。
郵政ユニオンの安達幸人副委員長は、「安定したサービスを提供するため、赤字となっている日本郵便の経営改善が必要だ。完全民営化を進めればサービスの維持がより困難となる。形態の見直しとともに、労働条件の改善を求めていく」とのべました。
自治労連の内田みどり中央執行委員は、「公立病院の職場では、劣悪な賃金勤務労働条件により、職員が確保できない病院もある。地域住民の暮らしと命に影響を及ぼす問題だ。職員を増やし、公の責任で安全なインフラ整備が必要だ」と求めました。
国公労連・全法務の亀岡希知書記長は、「法務局では新規施策による増員が得られたものの、年度当初の定員数と比較すればわずかな定数増にとどまり、定員不足を解消するには至っていない。必要な行政体制の確保へ引き続きとりくんでいきたい」と決意をのべました。
民間部会からは、福祉保育労、検数労連、生協労連の各代表が訴えました。また全労連から黒沢事務局長が駆けつけ、官民の共同宣伝行動に加わりました。
以 上 [...] Read more...
2025年2月17日高物価つづくもと賃上げ要求はさらに切実に
= 25年春闘統一要求書を政府・人事院に提出 =
公務労組連絡会は2月17日、政府・内閣人事局および人事院に対して、「月額28,000円以上、時間給200円以上」の賃上げをはじめとする25年春闘統一要求書を提出しました。
要求書提出には、香月事務局長、西・吹上の各事務局次長らが出席、政府・内閣人事局は渡辺耕次参事官補佐(写真右)が、人事院は吉田道代調査官がそれぞれ対応しました。
いますぐにでも賃金改善勧告を出せ
政府・内閣人事局への要求書提出にあたって香月事務局長は、「実質賃金は3年連続でマイナスとなり、昨今の高物価に賃上げが追いついていない。生活改善できる大幅賃上げは、待ったなしの課題だ」とのべ、使用者責任をふまえた今春闘での賃上げ回答を求めました。
人事院に対しては、「物価の高止まりの実態をふまえれば、夏まで待たずに、この春闘期に賃上げ勧告を出すべきだ。民間企業は4月に賃金が改定され、一方で公務員はクリスマスまで賃上げなしという現状を変えるため、人事院は真剣に検討せよ」と求めました。
これに対して、内閣人事局の渡辺参事官補佐は、「要求の趣旨は承った。要求事項は多岐にわたっているため、検討させていただいた上で、しかるべき時期に回答を行いたい」とのべました。
公務労組連絡会は賃上げなど切実な要求の実現にむけ、各地のとりくみを積み上げ、3月下旬での春闘期の回答引き出しに全力をあげます。
以 上
【添付資料】
(1)人事院あて2025年春闘統一要求書
(2)政府あて2025年春闘統一要求書
(3)公務員制度に関する要求書 [...] Read more...
2025年1月30日運動への共感の広がりに確信を持ってたたかおう
= 臨時総会を開いて25春闘方針と要求を確立 =
全労連公務部会・公務労組連絡会は1月29日、都内で臨時総会を開き25春闘にむけた運動方針と政府・人事院への要求を確立しました。
総会には、5単産18地方組織からの代表、幹事会など総数68名が参加しました。活発な討論を通して、物価高騰のなか今こそ大幅賃上げを勝ち取ろうと意思統一しました。
自民党の悪政を終わらせるチャンス!
臨時総会は、宮下直樹公務労組連絡会副議長が開会あいさつし、総会議長選出後に主催者を代表してあいさつした桜井眞吾公務労組連絡会議長は、「衆議院で与党が過半数割れするなか、夏の参議院選挙を控える25春闘は、政治そのものを大きく変えていくチャンスだ」といっそうの奮闘を呼びかけました。
来賓として全労連の秋山正臣議長、民間部会から岩城伸生協労連副委員長、日本共産党の塩川鉄也衆議院議員から、激励と連帯のあいさつを受けました。香月直之事務局長が25国民春闘方針案・要求案を提案、討論では14人が発言(別記)するもと、議案は満場一致で採決されました。
その後、「25国民春闘アピール」(別掲)を採択し、浅野龍一副議長(国公労連委員長)が閉会あいさつし、日巻直映代表委員(郵政ユニオン委員長)の発声で団結ガンバローを三唱し、25春闘を意気高くたたかう決意を固めあいました。
【討論(要旨)】
(1) 富山公務共闘(準備会)
地域手当について、一刻も早く再改正を求めていきたい。国会で教員の給特法の改訂がねらわれているが、時間外手当がないという根本的な問題が置き去りにされている。給特法を良いものにさせるために、今国会を「教育国会」として奮闘していきたい。
(2) 埼玉公務共闘
地域手当見直しで東京都に人材流出し、自治体職場の人材確保が厳しくなってしまう。保育の公定価格にも影響することから、埼玉県と埼玉市の人事委員会に改善要求書を提出し、国会議員35名に対して要請書を送付した。
(3) 千葉県公務労組連絡会
鳥インフルエンザの発生で、県庁職員が殺処分で忙殺されている。一方で、鳥インフルエンザを検査する4か所の衛生検査所を、2か所への統廃合がねらわれている。住民サービスの切り捨てを許さないために、職場からのたたかいで歯止めをかけていく決意だ。
(4) 長野県公務労組連絡会
民間給与実態調査は、比較する企業規模が中小まで幅広く対象となっている問題がある。労働組合のない企業も含まれている。公務と民間が連携して、賃金水準引上げを要求に掲げ、全国的な取り組みで中高年層を含めた改善を強く求めていきたい。
(5) 静岡県公務共闘
全国一律最賃の実現をめざすたたかいは、地域手当の支給率が自治体ごとに異なるという現状を変え、将来的には、地域手当を廃止して基本賃金に組み込むという展望を開くたたかいだ。そのためにも、全国すべての仲間が力を合わせていくことが重要だ。
(6) 大阪公務共闘
昨年の人事院勧告は32年ぶりのベースアップと言われているが、30代後半で引き上げ率が官民較差の2.76%を割り込み、40代以降では1%台にとどまった。基本賃金の引き上げであるベースアップ要求の実現にむけて、たたかいを強めよう。
(7) 滋賀公務共闘
賃金上昇に連動して指定管理料を増額する「賃金スライド制度」が、県内では草津市で初めて導入される。滋賀自治労連では県労連と共同して制度導入を求めてきた。管理料の増額分を賃金に適切に反映させるためにも、労働者の組織化をすすめたい。
(8) 山口県公務共闘
昨年12月に非正規公務員の労働相談ホットラインを実施した。残念ながら相談件数は少なかったが、公務職場の非正規労働者の賃金・労働条件の改善を社会的にアピールするためにも、こうした活動をがんばって継続していきたい。
(9) 日本医労連 原英彦副委員長
診療報酬の抑制、コロナ支援金の打ち切りなどで、夏季一時金、年末一時金の大幅なカットが全国的に起こった。どうしても負けられない25春闘という想いで、回答日翌日の統一ストライキを構えてたたかう方針を確認している。
(10) 郵政ユニオン 谷川紀子中執
最低賃金を引き上げるため、本部・地本が一体になって自治体への働きかけ、意見陳述等に取り組んできた。24春闘で時給制契約社員の賃上げがゼロ回答となるなか、今春闘もストライキを背景に、すべての社員の大幅な賃上げを求めたたかう。
(11) 自治労連 山本民子中執
昨年4月に診療報酬の改定があったが、一方では看護師の離職に歯止めがかからず、欠員状態で病床閉鎖を余儀なくされている公立病院も多い。全国どこでも同レベルの医療や介護が受けれるということが、憲法がかかげる社会保障の理念だ。
(12) 自治労連 前田博史副委員長
昨年は4つの県本部が増勢に転じた。労働組合が要求を前進させてきたことが背景にある。労働組合の活動が職場の隅々に伝わっているかがポイントだ。組織拡大をはじめ運動への結集を豊かにするため、25春闘では対話と学びあいを大いに進めていく決意だ。
(13) 国公労連 笠松鉄兵書記長
8月の人事院勧告から4か月以上も、勧告の取り扱いが店ざらしにされてきた。労働基本権剥奪のもと勧告制度の構造的欠陥が明らかとなっている。労働条件改善と労働基本権を結んだ職場学習をひろげ、すべての国公労働者を対象に組織拡大を進めていきたい。
(14) 全教 板橋由太朗中執
非正規の会計年度任用職員の加入が進むもと、組合員の増勢を実現した。スクールカウンセラー雇い止め問題で相談会を開くなど、丁寧に要求をつかみ対話をしたことが加入につながっている。現場の願いを反映した教育予算の実現へ、25春闘で奮闘していきたい。
以 上 25国民春闘アピール
本日、私たちは臨時総会を開催し、25年国民春闘方針を確立した。
日本の労働者は、賃上げが物価上昇に追いつかず、生活悪化がすすんでいる。一方、大企業の内部留保は約553兆円にも達している。内部留保の一部を賃金や国民生活にまわし、中小企業の価格転嫁に応じるなど、大企業に社会的責任を果たさせれば、大幅賃上げは十分可能である。
すべての労働者の生活改善につながる大幅賃上げ、全国一律最賃制と今すぐ時給1500円、労働時間短縮、労基法解体阻止、公共の再生と社会保障の充実、ジェンダー平等推進などの切実な要求をかかげ、その実現にむけて職場や地域で諸行動を展開しよう。
公務職場では、機械的な定員削減に慢性的な欠員が加わり、際限のない長時間労働が横行している。心身の健康を害し、休職や退職に追い込まれる仲間も後を絶たない。「公務の魅力」を取り戻すためにも、ゆとりある人員体制の実現とともに、すべての公務労働者の大幅賃上げ、世代や性別、地域、職種などのあらゆる格差を解消する賃金改善で、誰もが誇りを持って働き続けられる職場を実現しよう。
同時に、公務職場を支える非正規公務員が雇用不安と不合理な格差のなかで働いている。「3年目公募」の制限撤廃や、病気休暇の有給化など当事者と労働組合の共同の力で勝ち取った成果を確信にしながら、非正規公務員の無期雇用化・正規化と均等待遇を必ず勝ち取ろう。
さらに、政府には、ILO勧告にもとづく労働基本権回復にむけた労使協議を直ちに開始することを強く求める。
今も続く国際法違反のロシアのウクライナ侵攻などの無差別殺戮に対して憲法9条をもつ日本の政府として即時停戦と対話による解決にむけて積極的に働きかけるべきである。昨年の臨時国会で成立した補正予算には、能登半島の復旧・復興費の3倍にもなる8千億円超の軍事費が計上された。さらに25年度予算案には8兆7千億円もの軍事費が盛り込まれ、違憲の敵基地攻撃能力の保有などアメリカ言いなりの大軍拡・「戦争国家づくり」の加速が狙われている。また、民意を無視して進められる辺野古新基地建設は、大浦湾に広がる軟弱地盤の改良工事が本格化している。
昨年、日本被団協がノーベル平和賞を受賞し、広島・長崎への原爆投下から80年を迎える。武器や戦争では、国民の平和や安全は守れない。莫大な軍事費を国民生活にまわし、能登半島地震・豪雨被災地の復旧・復興を急ぐとともに、消費税減税・インボイス廃止、医療・介護・保育・年金など社会保障の充実、教育費無償化など、公務・公共サービス、教育の拡充をはかるべきである。
この間、全国の公務の仲間は、度重なる災害への対応、国民のいのちやくらし、教育を守るために現場で奮闘し、公務に対する信頼や理解を広げてきた。そして、公務労働者の大幅賃上げ、長時間労働の解消、非正規公務員の差別的な処遇の改善などを求める私たちの運動は、マスコミも注目し、共感や世論を広げ、政治や行政を大きく動かしてきた。
このことに確信をもち、25国民春闘で労働者の諸要求実現、国民が主人公の政治への転換をめざして、すべての職場と地域から全力で奮闘しよう。
2025年1月29日
全労連公務部会第34回・公務労組連絡会第68回臨時総会 [...] Read more...
2024年12月12日石破内閣は人員確保と予算増額を!
= 師走の繁華街で宣伝行動 =
全労連公務部会は12月12日夕刻、JR有楽町駅前で宣伝行動にとりくみました。クリスマスも近づき多くの人が帰りを急ぐ駅頭で、「あなたの声で 大幅賃上げへチェンジ!」と秋年ビラを配布しました。公務各単産から60人が参加しました。
全国どこでも公務公共職場の人員不足は深刻
公務部会の桜井眞吾代表委員は、「軍事費拡大による増税に加え、値上げが止まらず生活は苦しいままだ。賃金が上がったと言われているが、非正規雇用への置き換えで平均賃金は実質的には下がっている。生活改善できる社会をつくっていこう」と、宣伝カーの上から呼びかけました。
全教の壇原書記長は、「学校現場は長時間労働、過密労働により子供たちと十分に向き合うことができていない。現場を無視した政府方針では長時間労働は解消しない。人員と予算を費やすために力を尽くしたい」と発言、日本医労連の原副中央執行委員長は、「多くの病院が赤字経営で、賞与は20万円も下がった病院もある。このままでは医療崩壊、介護崩壊が起こる。ケア労働者の賃上げの実現で医療、介護を守るために声をあげてほしい」と訴えました。
郵政ユニオンの谷川中央執行委員は、「郵政職場の14万人の非正規社員は、物価高騰で苦しい生活をおくっている。時給は最低賃金プラスアルファほどしかない。なのに、休暇が取れないことが常態化。組合への加入を呼びかけている」とのべ、自治労連の内田中央執行委員は、「災害など緊急対応のため体制拡充が必要なのに、多くの自治体が人員不足により住民サービスを縮小せざるをえない。地域のみなさんといっしょに、命を守る政治と社会をつくるために声をあげよう」と力強く呼びかけました。また、国公労連・全労働の南副委員長は、高齢者に十分な処遇が保証されない国家公務員職場の問題を訴えました。
以 上 [...] Read more...
2024年12月11日「3年目公募」を廃止させた意義は大きい
= 非正規公務員をめぐって学習会を開催 =
全労連公務部会・公務労組連絡会は12月11日、「非正規公務員の公募問題を考えるオンライン学習会」を開催しました。
臨時・非常勤職員専門委員会からの問題提起をもとに、各単産からの現場からの報告で非正規公務員の現状を共有、今後の運動の方向を意思統一しました。
オンライン学習会には、100を超えるアクセスがありました。
当事者参加でねばり強く当局交渉を
主催者を代表して公務部会の宮下直樹代表委員は、「全労連の『非正規公務員ホットライン』には多様な相談が寄せられている。きょうは非正規公務員の切実な課題を取り上げて学習を深めたい」とあいさつしました。
賃金・権利専門委員会の笹ヶ瀬委員長による「期間業務職員の『3年公募要件』の廃止~その意義と諸課題について」と題した問題提起、自治労連の嶋林弘一中執からの地方自治体での会計年度任用職員にかかわる報告のあと、各組合からは職場の実態が具体的にのべられました(別掲)。
最後に公務部会の西事務局次長による、「学習会などを通して、『3年公募要件』撤廃を職場に知らせるとともに、非正規公務員も交えて当局とねばり強く交渉していく必要がある。さまざまな問題を広く訴えるために、職場や地域から宣伝行動にとりくもう」と行動提起をかねたまとめで学習会を締めくくりました。
[各組合からの報告]
○ 大阪自治労連・久保貴裕副委員長
秋季年末闘争で大阪府内27の自治体で正規、非正規職員の処遇改善のため労使交渉を行った。当事者の会計年度任用職員の組合員が交渉の場で訴え、大阪自治労連として統一交渉たたかったことで要求が前進。その成果が組織拡大につながった。
○ 全教・波岡知朗副委員長
短時間勤務の会計年度任用職員は、勤務日数の上限があるため、授業の準備等を勤務時間外で対応することが常態化している。職場環境の不備から退職者が後をたたず、子どもの教育に悪影響がでている。正規化を求めてとりくみを強めている。
○ 国公労連全厚生・渡名喜まゆ子執行委員
人手不足で長時間・過密労働が続いている。非正規の期間業務職員が正規職員の業務を任され、10年以上働いている人もいる。「3年公募要件」が撤廃されたが、一方で毎年公募になるのではないかと不安の声も聞かれる。
以上 [...] Read more...
2024年12月4日軍備増強ではなく国民の命と暮らしを守れ!
= 公務・公共サービス拡充へ要求行動 = 全労連公務部会は12月4日の退庁時間にあわせて、公務・公共サービス、教育を拡充するための予算拡充・大幅増員を求めて、財務省前での要求行動にとりくみました。
各単産から50人が参加し、帰宅する公務員や霞が関を往来する人々に横断幕でアピールしながら、宣伝ビラを配って要求実現を訴えました。 予算編成作業すすむ財務省に声を届ける 主催者を代表して、全労連公務部会の浅野龍一代表委員・国公労連委員長は、「石破内閣は、軍事費増大ではなく国民の暮らしを守るための予算編成を行うべきだ。公務・公共職場の人たちが安心して働ける環境をつくることが必要。そのためにも、予算と人員の拡充を求めていこう」と呼びかけました。 各組合からの訴えでは、「コロナ禍や災害がつづくなかにあっても、国立医療の職場では、給与改定なし、賞与改定なしという状況だ。安心・安全の医療体制のために、国として責任をもった財政の確立を求める」(全医労・鈴木中央執行委員)、「教職員の働き方の見直しが検討されているが、適正な人員に増やすことこそが求められている。問題は日本の教育予算が低すぎることであり、軍事費倍増ではなく教育予算を増額せよ」(全教・板橋中央執行委員)など、財務省に向かって声を上げました。 郵政ユニオン・谷川中央執行委員は、「郵便料金の値上げなどで郵便離れが進んでいる。一方で日本郵政は、経営判断の失敗による多額の損失を社員の犠牲により立て直しを図っている。利用者本位の郵便局、すべての社員が働きやすい職場をめざしてたたかう」と決意をのべ、自治労連・嶋林中央執行委員は、「能登半島地震では、いまだに復旧が進んでいない。地元の自治体職員、全国から派遣された職員も、長時間労働の限界に来ている。財務省は、住民のための予算をだだちに拡充せよ」とのべ、年末の予算案確定にむけて力強く訴えました。 最後に国公労連の関口中央執行委員のリードでシュプレヒコールを財務省にぶつけ、要求宣伝行動を終えました。 以 上
[...] Read more...